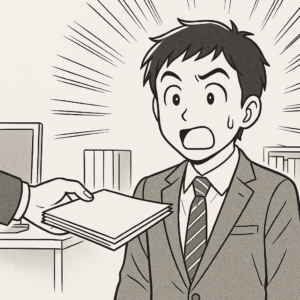新潟で「記念誌」の発注をご検討の方は、こちらのサービスページも是非、ご覧ください。
✅ 1章|記念誌の作り方がまるわかり!初心者でも安心の印刷ガイド【完全版】
「記念誌の担当をお願いしたいんだけど…」
突然そう言われて、戸惑っていませんか?
記念誌は、創立記念や卒業、地域行事、閉校など、人生や組織の節目をかたちに残す大切な冊子。でも、多くの方にとっては“はじめての仕事”です。何から始めればいいのか?誰に相談すればいいのか?原稿はどう集める?どこに印刷を頼む?——そんな悩みが次々と押し寄せてくるのが、記念誌づくりのリアルです。
このブログでは、**記念誌を初めて担当する方が「迷わず、効率よく、そして感動的な1冊を作るための道筋」**を、新潟の印刷会社である私たち新潟フレキソが徹底解説します。
企画や構成の立て方から、原稿・写真の集め方、レイアウトや印刷方法の選び方、納品スケジュールまで、すべての工程を網羅した**“作成ガイドの決定版”**です。
「初心者でも、ここまで読めば安心」そう思える実践的なチェックリストもご用意しています。
あなたの「わからない」を、「できる」に変える。そのお手伝いが、私たちの役目です。
✅ 第2章|記念誌とは?制作目的と種類をやさしく解説
「そもそも記念誌って何を載せるの?」「卒業アルバムとは違うの?」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
記念誌とは、ある出来事や節目の記録を“冊子”という形で残す、特別な出版物です。個人の思い出や組織の歴史、地域の活動の軌跡など、時間や想いを未来に届ける“タイムカプセル”のような存在ともいえます。
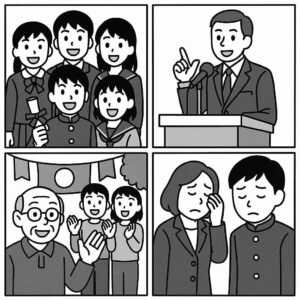
記念誌の制作目的はさまざまですが、大きく分けると以下のような種類があります:
-
創立・創業記念誌:企業や学校、団体などの〇周年を祝う節目に
-
卒業・卒団・閉校記念誌:学校やチームでの思い出や感謝を形に
-
地域活動・自治体記念誌:町内会、NPO、地域行事などの記録に
-
社史・周年報告書:企業が自社の歩みを振り返り、社内外に伝える
-
追悼・メモリアル記念誌:故人や創業者の功績を後世に伝えるため
-
学術・研究記録誌:学会や研究団体の活動の集大成として
このように、記念誌は「何を、誰に、どんな形で伝えたいか」によって、その中身や構成も大きく変わってきます。
つまり、記念誌づくりの第一歩は「目的」と「対象読者」を明確にすることから始まるのです。
私たち新潟フレキソでは、新潟県内の学校・企業・自治体をはじめ、さまざまな現場で記念誌制作をお手伝いしてきました。それぞれの目的に応じた構成・印刷仕様・ページ数の設計も、豊富な事例をもとにご提案可能です。
次の章では、「目的に合った記念誌の設計図をどう描くか?」=企画・構成の立て方を解説していきます。
✅ 第3章|記念誌の企画と構成をどう考える?成功のカギは“設計図”にあり!
記念誌づくりを成功させる最大のポイント――それは、**「企画と構成」**をしっかり固めてから動き出すことです。
なんとなく「写真を集めて、思い出を書いて、印刷すればいいんでしょ?」と思って始めてしまうと、途中で「ページ数が足りない!」「テーマがバラバラ!」という事態になりかねません。
記念誌は、いわばひとつの“本”をつくるプロジェクト。
だからこそ、設計図となる「企画」と「構成」は最初にじっくり考えておく必要があります。
■ まず考えるべきは「何を残したいか?」
記念誌の本質は、**“誰に、どんな想いを、どう残したいか”**という問いに答えることです。
-
節目を記録したいのか?
-
感謝の気持ちを届けたいのか?
-
歴史や実績を未来に伝えたいのか?
この「目的」が明確になると、どんな記事を載せるべきか、誰に寄稿してもらうか、写真は何を撮るか──すべての方針が見えてきます。
■ 構成パターンは大きく3タイプ
| パターン | 特長と向いている用途 |
|---|---|
| 時系列構成 | 創立〜現在までの歩みを年表的に記録/企業・学校の周年記念など |
| テーマ別構成 | 活動・部門ごとに章を分ける/複数寄稿者・多ジャンル向け |
| ストーリー型構成 | ひとつの人物・出来事に焦点を当てて物語形式に/創業者の軌跡・復興記録など |
■ 章立て例:学校の創立50周年記念誌
-
ごあいさつ(校長・理事長など)
-
沿革・年表(設立〜現在までの歩み)
-
校舎や制服の変遷
-
卒業生・教員のインタビュー
-
行事・部活動の紹介
-
地域との関わり
-
在校生からのメッセージ
-
編集後記・協力者一覧
構成をしっかり考えておくことで、原稿集めや写真選定、レイアウト作業も格段にスムーズになります。
次の章では、いよいよ実践編として「原稿・写真の集め方」とその注意点を解説します。
ここからが“現場担当者の腕の見せどころ”ですよ!
✅ 第4章|原稿・写真の集め方と注意点|記念誌づくり最大のヤマ場を乗り越える!
構成が決まったら、いよいよ**「中身=素材」**を集める段階へ。
記念誌制作で一番大変なのが、この「原稿・写真の集め方」だと言っても過言ではありません。
実際、多くの担当者がこんな悩みに直面します:
-
寄稿をお願いしたのに締切を過ぎても届かない…
-
写真の画質が悪くて印刷に使えない…
-
文章が短すぎたり、長すぎたりでページに合わない…
こうしたトラブルを防ぐには、「具体的な依頼」と「見える化された管理」がカギです。
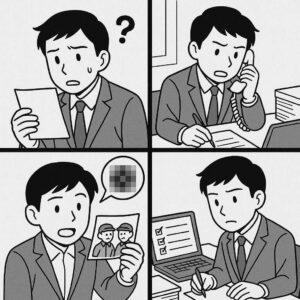
■ 原稿依頼は“伝え方”がすべて
単に「何か書いてください」ではNG。以下の項目を明確に伝えましょう:
-
テーマ例:「卒業の思い出」「〇〇周年に寄せて」など具体的に
-
文字数目安:600字以内/1,000字以内など
-
提出形式:Word/手書き可/メール添付など
-
締切日:余裕を持った期日+リマインド日
-
写真の有無:一緒に提出してもらうか確認
テンプレート(WordやPDF)を添えて依頼すれば、相手も安心して書けます。
■ 写真は「解像度」と「構図」が命!
スマホ写真は使いやすい反面、画質が足りない/構図が偏っているなどの落とし穴も。
-
2MB以上の解像度が理想
-
横向き推奨(誌面に収まりやすい)
-
被写体が中心で明るい写真を選ぶ
-
誰が写っているか/掲載OKかの確認も必須
紙焼き写真しかない場合は、スキャン対応もOK。
当社でもスキャン・補正・レイアウト提案まで一貫対応できます。
■ 管理表があるだけで全然違う!
原稿と写真の提出状況を一覧で把握できる表を用意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄稿者名 | 誰に頼んだか |
| 頼んだ日 | 依頼日時 |
| 原稿提出状況 | 済/未/確認中など |
| 写真提出状況 | 有/無/再依頼など |
| 備考 | コメント・差し替え希望など |
GoogleスプレッドシートやExcelでOK。共有すればチーム管理もスムーズに。
この章を乗り越えれば、記念誌はもう半分完成したようなもの。
次章では、素材をどう見せるか=「デザイン・レイアウト」のポイントを徹底解説します!
✅ 第5章|記念誌のデザイン・レイアウトのコツ|見やすさ・美しさ・想いが伝わる誌面に
せっかく集めた原稿や写真、どうせなら**“見た目でも心を動かす記念誌”**に仕上げたいですよね。
記念誌の印象は、内容だけでなく「デザイン」と「レイアウト」で大きく左右されます。
表紙の雰囲気、文字の読みやすさ、写真の配置──これらが整っていると、それだけで「丁寧につくられた一冊」という信頼感が生まれます。
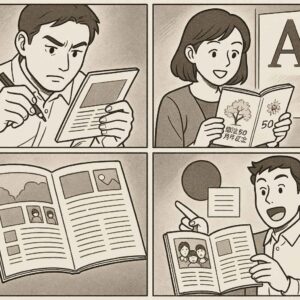
■ 読みやすさと雰囲気の決め手は「フォントとサイズ」
| 用途 | おすすめ書体 | 印象 |
|---|---|---|
| 表紙・タイトル | 明朝体 | 厳かな雰囲気、格調高い |
| 本文 | ゴシック体 | 読みやすく、フラットな印象 |
| キャプション | 丸ゴシック | 柔らかく、親しみやすい |
特に高齢の読者も想定する場合は、フォントサイズや行間、文字色と背景のコントラストにしっかり配慮しましょう。
■ 表紙は“顔”!キービジュアルとタイトル配置がカギ
-
校章・ロゴ・建物など象徴的な写真やイラストを中央に
-
「創立〇周年記念誌」「令和〇年度」などの文字は大きめ・明朝体で
-
キャッチコピーを入れると印象がぐっと強くなる
例:「未来へつなぐ50年の歩み」
■ ページ構成は“リズム”が命
全ページが文字だけだと重く、写真だけでも間が持たない。
文字ページと写真ページを交互に組む・余白を活かす・見出しを使って整理することがポイント。
-
1ページ1テーマに絞ると、すっきり見やすく
-
同じフォーマットを繰り返しすぎない(変化をつける)
-
「写真+短文+キャプション」の構成は鉄板
■ 写真レイアウトのコツ
-
主役の写真は大きく、他は小さくしてメリハリを
-
被写体の視線に合わせて配置方向を調整
-
キャプションは短くても意味が伝わるように
-
色調を整えると統一感が出る(補正対応も可)
もしデザインに自信がない場合でも、新潟フレキソではプロによる表紙デザイン・誌面レイアウトの提案も可能です。
「このパートだけ手伝ってほしい」というご相談でも大歓迎!
次章では、いよいよ記念誌完成までの最終ステップ──印刷準備と納品までの流れを解説します。
✅ 第6章|印刷の準備と納品までの流れ|入稿・校正・製本もまるっと解説!
すべての原稿と写真が揃い、デザインも完成!
ここまで来たら、いよいよ印刷会社とのやりとり=「印刷準備と納品」のフェーズです。
この章では、初心者でもスムーズに進められる印刷の基本的な流れと、よくあるつまずきポイントを解説します。

■ 入稿前にチェックしたい「データのまとめ方」
まず、印刷に出すための「入稿データ」を用意します。
入稿形式は以下の3つに分かれます:
-
完全データ入稿(PDFでレイアウト済み)
→ デザイナーが組んだ場合はこちら -
素材支給+レイアウト依頼(Word・写真などを渡して印刷会社におまかせ)
→ 一般的な記念誌担当者はこちらが主流です -
紙原稿入稿(手書き・印刷物をまとめて渡す)
→ スキャンや入力からお願いするケース
新潟フレキソではどの形式にも対応可能なので、「データがバラバラでもOK」です!
■ 校正(こうせい)とは?印刷前に絶対必要な作業
校正とは、誤字・脱字や内容の誤りを印刷前にチェックする作業です。
見落としがちなポイントはこちら:
-
名前や肩書きの漢字違い
-
写真とキャプションの組み合わせミス
-
ページ番号と目次のズレ
PDF形式で「仮刷り」を確認 → 紙に出力して複数人で見るのがおすすめ。
最終OKが出ると「校了(こうりょう)」と呼び、印刷工程に入ります。
■ 印刷仕様の決め方
-
部数:配布予定数+10〜20部の予備が目安
-
製本方法:
– 中綴じ(16〜40P程度)…ホチキス綴じ、安価・軽量
- 無線綴じ(40P以上)…背表紙あり、保存性高い -
用紙:
– 表紙:コート紙・マット紙など厚手
– 中面:上質紙・マット紙など読みやすさ重視 -
カラー/モノクロ:全部カラー or 一部だけカラーも可(コスト調整可)
■ 納品までのスケジュール感
| ステップ | 日数目安 |
|---|---|
| 校了後〜印刷 | 約3~5日 |
| 製本加工 | 約5~9日 |
| 検品・納品 | 約1~2日 |
→ 合計10〜16日が目安。
「卒業式に間に合わせたい」「記念式典の前に届いてほしい」など希望日がある場合は、最初の打合せ時に必ず伝えましょう。
新潟フレキソでは、データ作成から印刷・製本・納品まで一貫対応。
「納品まで不安なく進めたい」「ミスが出ないようにプロに見てもらいたい」そんなご希望も大歓迎です!
次章では、記念誌制作でよくある“困った”を解決するQ&Aコーナーをお届けします。
✅ 第7章|よくある質問&不安解消Q&A|「困った…」は誰もが通る道!
「何から手をつければいいのかわからない…」
「締切に間に合うか不安です…」
「こんなこと印刷会社に聞いていいのかな?」
大丈夫です。記念誌を作った人の9割以上が“初心者”としてスタートしています。
不安になるのは当たり前。ここでは、実際によくある質問をまとめて、新潟フレキソの現場目線でズバッとお答えします。
Q1. 時間がない!ギリギリでも間に合いますか?
A:まずはご相談ください。最短スケジュールをご提案します。
「あと1ヶ月しかない!」という方でも、ページ数や校正回数を絞って進行すれば十分可能です。
構成案テンプレや既存レイアウトの活用で、スピード感ある制作が可能です。
Q2. 原稿が集まりません…。どうしたら?
A:テンプレートや依頼文サンプルをご提供します。
「どう書けばいいかわからない」という寄稿者が多いのが現実。
テンプレと見本があるだけで提出率は劇的に上がります。
Q3. 写真が古い/ボケてるけど使えますか?
A:補正・加工で見違えるほどきれいになります。
暗い・ぼやけた・傾いている写真も、専用ソフトで補正可能です。
人物にモザイク処理や背景ぼかしなども対応しています。
Q4. 誤字脱字が不安。あとから直せますか?
A:校正段階ならOKですが、印刷後は修正できません。
だからこそ校正作業が最重要です。PDFで仮刷り→紙で確認→複数人でチェック。
この流れで誤植の大半は防げます。
Q5. データの作り方がわかりません…。
A:手書き原稿でもOK!データ化もレイアウトも丸ごとお任せください。
Word・Excel・手書きなど、どんな状態でも印刷可能な形式に整えます。
「どこまで頼んでいいか不安」という方こそ、お気軽にどうぞ。
あなたの不安や疑問は、きっと誰かも通った道。
だからこそ、「こんなこと聞いていいのかな?」と思ったら、まずご相談ください。
新潟フレキソでは、そんな一歩を応援する準備が整っています。
✅ 第8章|まとめ|あなたの頑張りは、必ず“誰かの宝物”になる
ここまで読んできたあなたは、もう立派な記念誌担当者です。
知識ゼロ、経験ゼロでも、「どうにか形にしたい」という想いがあれば、それだけで記念誌づくりのスタートラインに立てます。
そして今、あなたはその一歩を確実に踏み出しました。
記念誌は、単なる冊子ではありません。
創立・卒業・閉校・地域行事──そこには、誰かの記憶、感謝、願い、誇りが詰まっています。
それを「目に見える形」にすることができるのが、記念誌という仕事の魅力です。
集める手間、締切のプレッシャー、校正の緊張感……
途中で「もう無理かも」と思う瞬間も、きっとあるでしょう。
でも、完成した冊子を手にしたとき、
きっとあなたはこう思うはずです。
「やってよかった」
そしてその一冊は、10年後、20年後に開かれても、
当時の空気や想いを鮮やかに蘇らせてくれる“宝物”になります。
私たち新潟フレキソは、あなたの「やってよかった」の瞬間を全力で支えるパートナーです。
まだ構成が決まっていなくても、写真が揃っていなくても、大丈夫。
「ちょっと相談してみたい」そんな一言から、すべてが始まります。

📋 記念誌制作チェックリスト&進行表
| ステップ | 項目 | 内容のポイント |
|---|---|---|
| STEP1-1 | 制作目的の確認 | 周年・卒業・地域活動などの目的を明確にする |
| STEP1-2 | 配布対象と部数の検討 | 配布対象(全校生徒、OB、地域など)と必要部数を想定 |
| STEP2-1 | 章立て(構成案)の作成 | 章立てや構成パターン(時系列・テーマ別等)を検討 |
| STEP2-2 | ページ数・サイズの設定 | A4/B5やページ数を仮決定して紙面設計へ |
| STEP3-1 | 寄稿依頼リストの作成 | 寄稿者や提供者を一覧化し、役割分担と依頼を明確に |
| STEP3-2 | テンプレート作成・配布 | テンプレート・提出ガイドラインを用意して送付 |
| STEP3-3 | 写真・資料の収集・管理 | 写真の画質・肖像権・スキャン作業などを整理 |
| STEP4-1 | フォント・色・雰囲気の決定 | 読みやすさやイメージに合ったフォント・色選定 |
| STEP4-2 | 見出し・余白・構成バランス調整 | レイアウトの統一感・視線誘導を意識した設計 |
| STEP4-3 | 表紙デザイン案の検討 | 表紙のキービジュアル・タイトル配置を検討 |
| STEP5-1 | 入稿形式の確認 | 完全データor素材渡しなど制作方式を決定 |
| STEP5-2 | 紙の種類・製本方式の選定 | 表紙と本文の用紙選び、綴じ方を用途に合わせて調整 |
| STEP5-3 | 見積もり依頼・予算調整 | 想定予算内での仕様調整と印刷費確認 |
| STEP6-1 | 仮刷りPDFで校正 | PDFで仮レイアウトを出力し、紙でも確認 |
| STEP6-2 | 複数人での誤字脱字・事実確認 | 肩書・名前・日付・内容など事実の再チェック |
| STEP7-1 | 納品日から逆算したスケジュール設計 | 式典や配布日に合わせた納品スケジュール逆算 |
| STEP7-2 | 納品形態と配送先の確認 | 納品先(学校・自治会館など)と数量を事前確認 |
| STEP8-1 | Q&Aの共有とマニュアル準備 | よくある質問を共有し、担当者引き継ぎ資料も準備 |
| STEP8-2 | トラブル発生時の対応方針確認 | 予備対応・誤植・遅延時の緊急連絡ルート整備 |
| STEP9-1 | 完成品の最終チェック | 刷り上がり冊子を現物確認し、問題ないか確認 |
| STEP9-2 | 配布物の仕分け・案内書同梱 | 配布先ごとに梱包・案内資料・封入物を仕分ける |
\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/
あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!
記念誌や印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。
▶ 会社概要はこちら
▶ [お電話でのご相談はこちら:025-385-4677]
↑オリジーではTシャツやグッズを作成してます!インスタで作品公開してます!
🔗関連リンクはこちらから
■金・銀・メタリックカラー印刷が小ロットでもOK!箔押し不要で高級感を出す新常識|新潟の印刷会社
■複写紙とは?仕組み・種類・印刷方法・カーボン紙との違いを徹底解説【減感加工も対応】
■地域をつなぐ!コミュニティ協議会広報誌の作り方【完全ガイド】|新潟フレキソが応援します!
■新潟で卓上カレンダーを名入れ・オリジナル制作するなら新潟フレキソ
■PTA広報誌の作り方 完全ガイド|新潟市の印刷会社が教える編集・構成・原稿文例・チェックリスト付き
■封筒の在庫管理完全ガイド|適正ロット数・在庫切れ防止・発注ミスを防ぐ方法を徹底解説!
■納品書とは?書き方・送り方・保存義務・電子保存・法律まで完全ガイド|印刷会社がマナーと実務を徹底解説!
■名入れカレンダー 新潟|壁掛けタイプの販促ツール印刷なら株式会社新潟フレキソにお任せ!
■【完全保存版|角2封筒とは】A4対応サイズ・切手代・郵便料金・書き方・横書きマナーまで全網羅!2025年最新ガイド