はじめに|なぜ今、「封筒の歴史」を知る意味があるのか?
あなたのデスクの引き出しにも、きっと一枚はあるであろう「封筒」。
請求書、案内状、履歴書、ちょっとした手紙――封筒は、私たちの暮らしやビジネスに当たり前のように溶け込んでいます。
でも、ふと思いませんか?
この「封筒」って、一体いつからあるのだろう?
なぜ、人はわざわざ“紙で包んで、封をする”という行為を大切にしてきたのだろう?
実はこの素朴な疑問の先には、**人類の「伝える力」と「守る文化」**の深い物語が広がっているのです。
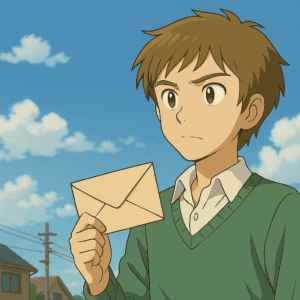
私たちは、封筒をただの紙袋だと思いがちです。
しかし、その形や使い方、封をするという行為には、長い歴史と豊かな文化的背景が隠されています。
たとえば紀元前2000年のメソポタミアでは、粘土で情報を包み込む“封筒”が存在していました。
中国では、紙の発明とともに“信封”という美しい礼の形式が確立され、
ヨーロッパでは、封蝋と印章が手紙の“正しさ”と“秘密”を守るための証になりました。
そして日本では、封筒という言葉が生まれるはるか以前から、
香を焚きしめた和紙で想いを包む「文包み」という文化が息づいていました。
本ブログでは、そんな封筒の起源と進化の道のりを、世界と日本の両方から徹底的にひも解いていきます。
単なる歴史の紹介ではありません。
「封筒が社会に与えてきたインパクト」「信頼と形式を支えてきた背景」
そして「今なぜ、デジタル時代においても封筒が必要なのか」まで、総合的にご紹介します。
たった一枚の紙の裏には、**千年以上の知恵と工夫、そして“人と人をつなぐ力”**が詰まっています。
封筒の歴史を知ることは、実は――
私たち自身の“伝える力”と“信頼のかたち”を見直す旅なのです。
第1章|封筒のはじまりを世界の歴史からたどろう
1. 粘土でできた最初の“封筒”!?──メソポタミアの不思議な記録方法
今から5000年以上前のこと。
チグリス川とユーフラテス川のあいだに広がっていたメソポタミア文明では、人々が物のやりとりを記録するために、とってもユニークな方法を使っていました。
それが、「粘土の球(ブッラエ)」です。
小さな丸い粘土の中に、石や粘土でできた“しるし”(トークン)を入れ、それが「牛が3頭」「麦が10袋」といった意味を持っていました。
そして、粘土の外側には印章を押して、誰が送ったものかがわかるようにしていました。
この「中身が見えない粘土のかたまり」は、現代の**“セキュリティ封筒”のような役割**を果たしていたんです。
壊さないと中身が見られない、でも壊せば中身がちゃんと確認できる――
人類が「情報を守りながら、相手に渡す方法」を初めて考えた瞬間と言えるかもしれません。
2. 粘土の手紙をさらに粘土で包む!?──本格的な“封筒”が登場した時代
その後、メソポタミアでは「楔形文字(くさびがたもじ)」を粘土板に刻むことで、文章での記録ができるようになります。
すると今度は、その粘土板を、さらに別の薄い粘土で包んでしまうという、まさに「封筒」らしい形が登場します!
しかもこの粘土封筒、表面には送り主の名前や相手の名前、場合によっては取引の内容まで書かれていて、内容が勝手に書き換えられないよう、信頼を担保する仕組みがありました。
つまり、封筒というアイテムは、もうこの時代から
「中身を守る」
「改ざんを防ぐ」
「相手にきちんと届ける」
という、今とほとんど同じ役割を持っていたんですね。

3. 中国・後漢時代の「紙」と「信封」──文化としての“封じる”が始まった
さて場所は変わって東アジア。
中国の後漢(ごかん)という時代、西暦100年ごろに登場したのが、「紙」という画期的な素材です。
この紙を改良して大量に使えるようにしたのが、宦官(かんがん)だった**蔡倫(さいりん)**という人物。
彼の技術によって、竹や木でできた硬くて重たい“書類”から、軽くて折りたためる紙の手紙へと、時代が進んでいきます。
そしてこの紙文化の中から生まれたのが、「信封(しんぷう)」という封筒のはじまりです。
信封とは、手紙を紙で包み、糊や印章(いんしょう)で封をするという、中国ならではの礼儀を伴ったスタイル。
身分が高い人や役所では、これを使うことで
「この手紙は正式なものですよ」
「誰にも中身を見られずに届けました」
という証になったのです。
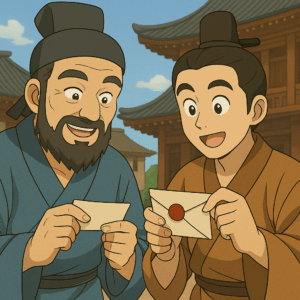
▶併せて読みたい記事 蔡倫とは|紙を発明した中国の天才発明家の歴史と世界への影響を新潟の印刷会社が解説【世界史にも登場】
4. ヨーロッパの“封蝋(ふうろう)”文化──封筒ではなくロウで封をする時代
ヨーロッパでは、封筒の形になるのはまだ先の話。
中世(12〜15世紀)では、紙を折って、その合わせ目にロウ(蝋)を垂らし、上から印章を押すという「封蝋」の文化が広まりました。
この封蝋は、文書が「正しいもの」「誰かに勝手に開けられていないもの」という証拠になります。
しかも、ロウの色にも意味があったんです!
-
赤:王様や貴族など、身分の高い人の手紙
-
黒:亡くなった人に関する文書(お悔やみなど)
-
金や銀:とても大切な儀式的文書
まさに封蝋そのものが、**差出人の身分や意図を伝える“シンボル”**だったのですね。

5. 恋の手紙と香りの演出──ロマンチックな封蝋の使われ方
15世紀を過ぎ、ルネサンス期になると、封蝋は“愛の手紙”でも大活躍します。
赤いロウにハート型の印、香水をかけた封…そんなラブレターがヨーロッパ中を飛び交いました。
日本の平安時代にも、香を焚きしめた「文(ふみ)」を折って届ける文化がありましたが、世界のあちこちで“香りで想いを伝える”封文化が自然に生まれていたのはとても興味深いですよね。
6. そして産業革命で封筒が“みんなのもの”になった
17〜18世紀になると、紙の値段が安くなり、印刷技術や工場の力も発達していきます。
そこで登場するのが、「紙の袋状の封筒」です。
最初は手作りだったので高価でしたが、19世紀のイギリスで封筒製造機が発明され、大量生産ができるように!
さらに1840年、「ペニーポスト」という制度がスタートし、封筒を使った郵便が誰でも使える社会のインフラとして定着していきました。
7. 封筒が社会にもたらした、目に見えない“すごい変化”
封筒が広まったことによって、実は私たちの暮らしや社会は、こんなにも変わっていきました:
-
個人の気持ちを安全に伝えられるようになった
→ 恋文も、感謝も、心のうちを安心して書けるように -
大切な情報が守られるようになった
→ 政府の書類、企業の契約書、裁判文書などが安全に届く -
手紙に“礼儀”や“信用”が宿るようになった
→ 封筒がきちんと閉じられている=誠意が伝わる、の証に
まとめ|封筒って、すごい発明だった!
いま、何気なく使っている一枚の封筒。
でもその背景には、人類が何千年もかけて工夫してきた、「伝えることを、きちんと・安全に・丁寧に行うための知恵」がぎっしり詰まっています。
粘土からはじまり、紙、ロウ、香り、そして機械化。
封筒は、**文明とともに進化してきた「心を包むツール」**なのです。
封筒の歴史 年表(世界編)
| 年代 | 地域 | 出来事 |
|---|---|---|
| 紀元前3500年頃 | メソポタミア | 粘土製のトークン「ブッラエ」を粘土で包み、印章で封印。最初の“封筒”の原型が登場。 |
| 紀元前2000年頃 | メソポタミア | 楔形文字を刻んだ粘土板を、さらに薄い粘土で包み封印。封筒としての形がより明確に。 |
| 西暦105年頃 | 中国(後漢) | 宦官・蔡倫が紙の製法を改良し、紙文化が広がり始める。 |
| 唐代(618〜907年) | 中国 | 手紙を紙で包む“信封”の文化が定着。糊や印章を使った封の形式が官僚社会に広がる。 |
| 12〜15世紀 | ヨーロッパ | 封蝋(ロウと印章)を使って文書を封じる習慣が一般化。封蝋の色・形で地位や用途を示す文化が確立。 |
| 17世紀 | ヨーロッパ | 紙の袋状封筒が登場。まだ手作りで高価だが、封蝋に代わる新しいスタイルとして普及が始まる。 |
| 1837年 | イギリス | 封筒製造機が発明され、封筒の大量生産が可能に。普及への大きな転換点。 |
| 1840年 | イギリス | 「ペニーポスト制度」導入により、封筒付き郵便が庶民にも普及。封筒が“誰でも使える道具”に。 |
第2章|日本の封筒文化──「包む」という心のかたちをたどる
平安時代(794〜1185年)
文包み(ふみづつみ)と香りの手紙文化
日本の封筒文化の原点は、華やかな貴族文化が花開いた平安時代にあります。
当時の人々は、今のような袋状の封筒を使っていたわけではありませんが、すでに「手紙を美しく包む」文化はありました。
それが「文包み(ふみづつみ)」です。
恋文や贈り物の文書は、和紙で丁寧に折り畳み、さらに香を焚きしめて仕上げるのが習わしでした。
この「焚きしめる」とは、お香を染み込ませたり、文を香炉の煙にあてたりして、香りごと想いを届ける演出のこと。
しかも、折り方にも意味がありました。
たとえば折り目が浅いと「控えめな好意」、深く丁寧だと「真剣な愛情」など、折りの角度や重なり方で、微妙な気持ちを表現していたのです。
これはまさに、封筒を超えた“芸術”。
視覚・触覚・嗅覚までを使って気持ちを包む、世界でも類を見ないほど繊細で奥深い文化でした。
鎌倉〜室町時代(1185〜1573年)
武士が守った“文書の厳しさ”と封緘文化
時代が下って武家社会となると、文書は“感情”よりも“命令”や“証明”のために使われるようになります。
この時代には、密書や命令書、通達文書などを糊付けして封じ、封緘(ふうかん)紙や印鑑で改ざんを防ぐ文化が定着してきます。
特に大名や幕府の使者などが使う文書には、
-
家紋入りの封緘紙
-
個人を示す「花押(かおう)」
-
開封時に破れてわかるような仕組み
が用いられ、「この封が破れていたら偽文書」と判断する社会的ルールが生まれました。
いわば、これが現代の「開封厳禁」「親展」や「セキュリティシール」の元祖。
信頼と権威を可視化する、封筒的な仕組みが日本独自のかたちで発展していったのです。
江戸時代(1603〜1868年)
書状箱と飛脚による“箱文化”の伝達スタイル
江戸時代に入ると、町人や商人も文書を頻繁にやり取りするようになりますが、この時代でも“袋状の封筒”はまだ一般的ではありませんでした。
多くの手紙は、
-
巻紙(まきがみ)または折り紙(おりがみ)に筆で書く
-
折ってから糊や紐で止める
-
さらに「書状箱(しょじょうばこ)」という木の箱に入れて
-
**飛脚(ひきゃく)**が運ぶ
というスタイルでした。
なかには、漆(うるし)で塗られた豪華な箱や、細工が施された特注の箱もあり、
「どんな箱で届くか」が手紙の格や差出人の地位を表していました。
今で言えば、高級ブランドの紙袋やギフトボックスのようなイメージです。
“包む”ことが、そのまま“伝える”という意味を持つようになっていたのです。
明治時代(1868〜1912年)
郵便制度とともに洋封筒が日本へやってきた!
日本に「封筒らしい封筒」が登場したのは、近代郵便制度が確立された明治時代のこと。
1871年、前島密(まえじま ひそか)の提唱により、日本の郵便制度が本格スタート。
その際、手紙をより安全に・きちんと届けるために導入されたのが、西洋から来た**洋封筒(ようふうとう)**です。
洋封筒は、それまでの折るだけの手紙とは違い、
-
横長の袋状で
-
のり付けできて
-
封印性が高い
という特徴がありました。
このスタイルはすぐにビジネス文書や公文書に取り入れられ、**「ちゃんとしている手紙=封筒入りの手紙」**というイメージが定着していきます。
さらに封筒には、
-
差出人の住所・氏名の印刷
-
社名入りのロゴ
-
装飾的なフレームデザイン
などが登場し、今で言う**「ブランディングされた封筒」**のはしりとなりました。
大正〜昭和(1912〜1989年)
大量生産とともに封筒が“生活の道具”に変化
大正・昭和期になると、封筒は印刷技術の発達と共に大量生産され、学校・会社・家庭などあらゆる場所で使われる「生活必需品」へと進化します。
この時代には、
-
クラフト紙(茶封筒)
-
カラー封筒
-
窓付き封筒(給与明細など)
-
名入れ封筒(企業・団体用)
といった封筒の“多様化”が進み、用途別に封筒を使い分ける文化が広まりました。
封筒はこの時点で、もはや“手紙を守るだけ”ではなく、
-
会社の信頼を伝える
-
内容の重要性を示す
-
開ける前から「何かが届いた」ワクワク感をつくる
そんな**“伝える道具”そのもの**になっていたのです。
📝コラム:和封筒って、実は“後から”登場したんです!
今ではすっかり日本の定番となっている「縦型の封筒」。
冠婚葬祭、お礼状、町内会のお知らせ…
「縦書きがしっくりくる封筒」として、暮らしの中に溶け込んでいますよね。
でも実は――
日本で最初に広まった封筒って、“横型”の洋封筒だったってご存じですか?
その始まりは、明治4年(1871年)に導入された近代郵便制度。
欧米スタイルをベースにしたこの制度と一緒に、**三角フラップ付きの洋封筒(横長・長辺開き)**が“標準”として導入されたのです。
当時の手紙は横書きも増えてきており、ビジネス文書や役所関係では、**横型封筒が「かっこいい」「文明的」**とされていました。
ところが、時代が進むにつれて――
「日本語はやっぱり縦書きが自然だよね」
「三つ折り便箋がピタッと収まる縦長が便利だね」
という声が広まり、日本独自の“和封筒”スタイルが逆輸入のように登場します。
そして昭和に入る頃には、
-
長3封筒(A4三つ折り対応)
-
長4封筒(B5三つ折り対応)
などがJIS規格として定着し、**今や封筒全体の約8割以上が縦型(和封筒)**という調査もあるほど、日常に溶け込んでいきました。
つまり和封筒は、
ただの「伝統」ではなく、
“日本の暮らしに合わせて進化した”最新形の封筒とも言えるのです。
現代(平成〜令和)
デジタル時代でも、封筒は“人の心”を運び続けている
今やメール・LINE・チャットで何でもすぐに送れる時代。
でも――封筒は、なくなっていません。
むしろ、「あえて封筒で渡す」ことに意味がある場面が増えています。
たとえば…
-
就職の内定通知
-
入学や合格のお知らせ
-
お礼やお詫びの正式な手紙
-
結婚式の招待状や役所からの通知
封筒には、「これから読むものは大事な内容ですよ」という**“空気をつくる力”**があります。
デジタルの速さとは違う、手間や重みが伝わることで、「気持ちが乗る」のが封筒のすごさなんです。
まとめ|“封筒”は日本人の心遣いそのものだった
日本では、昔から「包む」という行為そのものに意味がありました。
-
平安時代:香りで想いを届ける
-
鎌倉時代:封で信頼を守る
-
江戸時代:箱で品格を示す
-
明治以降:封筒で“きちんと感”を伝える
そして今もなお、封筒は私たちの気持ちを、ちゃんと相手に伝えてくれる道具として、静かに役割を果たしています。
第3章|封筒の種類・形・素材の進化と、その“意味”
1. 形状の違い:縦型 vs 横型、それぞれの“役割”
封筒には大きく分けて**「縦型(和封筒)」と「横型(洋封筒)」**の2種類があります。
-
縦型封筒(和封筒)
-
封入口が短辺(上側)
-
日本語の縦書きに適している
-
「長3封筒」や「角2封筒」などが代表格
-
学校・町内会・ビジネス書類など、正式な印象
-
-
横型封筒(洋封筒)
-
封入口が長辺(横側)
-
英文・横書き書類との相性が良い
-
招待状、案内状、私信などに使われることも多い
-
「ダイヤ貼り(V字フラップ)」で見た目が華やか
-
それぞれの形状には**“入れるものの向き”や“届ける相手との関係性”**が大きく関係しているんです。
2. サイズのバリエーション:なぜ「長3」「角2」って呼ぶの?
「長3封筒」や「角2封筒」など、封筒には独特なサイズ呼称がありますが、これはJIS(日本工業規格)で定められた表記です。
| 封筒の種類 | 主な用途 | 対応用紙サイズ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 長3封筒 | 請求書・案内状・ビジネス文書 | A4三つ折り | 定型郵便に収まる万能選手 |
| 長4封筒 | 手紙・通知 | B5三つ折り | 学校のお便りによく使われる |
| 角2封筒 | 資料送付・パンフレット | A4そのまま | 折らずに送れる大容量封筒 |
| 洋2封筒 | 招待状・挨拶状 | はがき・カード類 | 横型・華やかな印象 |
このように、何を入れるか、どう送るかで封筒の選び方がまったく変わるんです。
📝コラム:長3・角2ってなに?封筒サイズの“謎ネーミング”を解明!
普段なにげなく使っている「長3封筒」や「角2封筒」という名前。
でもよく考えると、「長」ってなに?「角」って?「3」とか「2」って、どういう意味?って気になりませんか?
実はこれ、JIS規格(日本産業規格)によって決められたネーミングなんです!
■「長(なが)」ってなに?
「長」は、“長形(ちょうけい)封筒”の略です。
これは封筒の縦横比が細長い(=縦長)スタイルを指します。
いわゆる“和封筒”と呼ばれる、縦書き文化にぴったりなスタイルですね。
■「角(かく)」ってなに?
「角」は、“角形(かくけい)封筒”の略です。
これは封筒の角がしっかりしていて、ほぼ長方形 or 正方形に近い形をしているもの。
折りたたまずに書類(A4など)をそのまま入れたいときに使われます。
■「3」や「2」って何の数字?
これは**対応する用紙サイズに基づいた“種類番号”**です!
たとえば…
-
長3封筒 → A4用紙を三つ折りしてピッタリ入る → 3番目に使われるサイズ
-
角2封筒 → A4用紙を折らずにそのまま入る → 2番目によく使われるサイズ
つまり、「長3」は“細長い形で3番目によく使われるサイズ”という意味なんです。
おまけ:サイズ名の覚え方ワンポイント
| 名前 | 意味 | 主な使い方 |
|---|---|---|
| 長3封筒 | 長形3号(A4三つ折り) | 会社の請求書や学校のお知らせ |
| 長4封筒 | 長形4号(B5三つ折り) | 個人の手紙、町内会のお知らせ |
| 角2封筒 | 角形2号(A4そのまま) | 履歴書、契約書、パンフレット |
| 洋2封筒 | 洋形2号(横型) | 招待状や挨拶状などおしゃれ封筒 |
まとめ
「長」=細長い封筒、「角」=角がしっかりした封筒、
そして数字はそのカテゴリ内での代表的なサイズ番号だったんですね!
今後、封筒を選ぶときに「名前の意味がわかるだけでちょっと楽しくなる」かもしれませんよ!
3. 素材の違い:クラフト・ケント・カラー封筒の“使い分け”
封筒の素材も目的によってさまざまです。
-
クラフト紙封筒(茶封筒)
-
安価で丈夫
-
請求書や見積書、事務的な送付に最適
-
実用重視
-
-
ケント紙封筒(白封筒)
-
上質で清潔感がある
-
礼状、案内状、ビジネス文書など“きちんと感”を出したいときに
-
-
カラー封筒
-
色のバリエーションで印象が変わる
-
結婚式の案内や、店舗のDM、ブランドイメージを大切にする場面で使用
-
-
特殊紙(パール、ユポ、和紙など)
-
高級感・個性・防水性などを持つ
-
芸術作品、招待状、こだわりのあるDMなどに使われる
-
素材の選び方ひとつで、「誰に」「どんな印象を届けるか」が大きく変わるんですね。
4. 特殊加工:窓付き・地紋入り・二重構造の進化
最近は、封筒にもさまざまな加工技術が取り入れられています。
-
窓付き封筒
-
中の書類の宛名がそのまま見える
-
請求書・明細書の送付に便利
-
作業効率&セキュリティ性UP
-
-
地紋入り封筒
-
中身が透けないよう内側に模様が印刷されている
-
情報漏洩防止、プライバシー配慮に◎
-
-
二重封筒
-
給与明細や機密文書に使われる
-
開封されたことがわかりやすい仕様も
-
これらはすべて、「受け取る相手の安心感や、差出人の信頼感」を守るために生まれてきた工夫です。
▶併せて読みたい記事 窓付き封筒の歴史|アメリカで誕生した“宛名が見える”仕組みの発明と普及の理由
5. 機械対応の進化:自動封入・OCR読み取りにも適応!
企業で大量に郵送するような場合、封筒は「機械で封入封緘できるかどうか」がとても重要です。
-
一定の紙厚
-
糊の付き方(アラビックのり or 両面テープ)
-
折りしろやフラップの角度
これらがすべて機械対応設計されている「機械封筒」も登場しており、
今や封筒はアナログとデジタルの接点として進化しています。
まとめ|封筒は「伝え方」をデザインできるツールだった!
封筒の種類、形、サイズ、素材、加工…
こうして見ると、封筒って**“紙の袋”以上に奥深い存在**ですよね。
何を、誰に、どんな気持ちで届けたいか。
それをかたちにしてくれるのが、封筒なんです。
第4章|デジタル時代にも“封筒”が必要とされる理由とは?
1. 「もうLINEでよくない?」という問いへの答え
現代社会では、スマホひとつでなんでも送れる時代です。
LINE、メール、クラウド、チャットツール…どんな情報も一瞬で届きます。
では、封筒に入れて手紙を送る必要なんて、もうないのでは?
たしかに、スピードやコストだけで見れば「デジタル一択」に見えるかもしれません。
でも、実際には今もなお、多くの場面で**「紙の封筒で届ける」ことが選ばれています。**
なぜでしょうか?
2. 封筒には「温度」がある
それは、封筒には“感情”や“信頼”が宿るからです。
-
ビジネス書類がきっちり封筒で届くと、「正式な対応をしてくれた」と感じる
-
お礼状やお詫び状が封筒に入っていると、「手間をかけてくれた」と伝わる
-
就職内定の通知が封筒で届くと、「大切に扱ってくれた」と思える
封筒は、送る人の姿勢を“形”にして届けてくれる道具なんです。
3. デジタル時代に広がる「紙封筒」の新しい価値
近年では、封筒に対するニーズが**「単なる郵送用具」から「コミュニケーションの演出ツール」へ**変わってきています。
たとえば:
-
ブランドデザインされた封筒 → 企業の第一印象をつくる
-
クラフト封筒+手書きメッセージ → ファンへの心のこもったDM
-
カラフルなカラー封筒やトレーシング封筒 → SNS映えするパッケージ
さらに最近では、**開封体験(アンボクシング)そのものが「マーケティング体験」**として注目されるようになりました。
紙の封筒でしか味わえない、開ける前のドキドキ、指先の感覚、紙の匂い…
**五感に触れる“リアルな体験”**が、どんどん価値を持つ時代になっているんです。
4. 封筒 × テクノロジーで進化中!
さらにおもしろいのが、紙の封筒が**“デジタルと融合し始めている”**ということ。
こんな新しい封筒、もう登場してます:
-
QRコード印刷でWebサイトや動画と連動
-
ARマーカー封筒でスマホをかざすと3D映像が浮かぶ
-
スマート封筒:開封時に中の情報がクラウドに通知される
まさに、封筒が「紙」から「インターフェース」へと進化しているんですね。
5. 封筒は“信用と気持ち”を運ぶ最後のリアルメディア
いまやどんな情報もデジタル化できる時代ですが、
“本当に大事なもの”って、やっぱり手元に残しておきたくなりませんか?
-
お祝いの手紙
-
入学通知
-
感謝の言葉
-
最後の別れの手紙
封筒は、そんな**「人の想い」を、丁寧に、確実に、そして美しく届けてくれる**存在です。
だからこそ今、紙の封筒が持つ**“伝える力”**が、むしろ見直されているのです。
まとめ|封筒はこれからも「人と人をつなぐ橋」になる
たとえ社会がどれだけデジタルに進んでも、
封筒は、心を包むための道具として生き続けるでしょう。
-
送る人の気持ちを“形”にし、
-
受け取る人の手に“信頼”として届き、
-
未来の“記憶”として残っていく。
封筒は、人と人のつながりの中で、これからも大切な役割を果たしていくはずです。
株式会社新潟フレキソは新潟市の印刷会社です。
封筒印刷のご注文も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
▶ 会社概要はこちら
🔗関連リンクはこちらから
- 連続抄紙機(れんぞくしょうしき)で紙の歴史を変えたルイ=ニコラ・ローベル|世界を動かした発明と奇跡の物語
- 窓付き封筒の歴史|アメリカで誕生した“宛名が見える”仕組みの発明と普及の理由
- 蔡倫とは|紙を発明した中国の天才発明家の歴史と世界への影響を新潟の印刷会社が解説【世界史にも登場】
- なぜ茶封筒は“失礼”とされるのか?白封筒との違いとマナーの正解を印刷会社が解説
- C判とは?A判を包む封筒サイズの国際規格を新潟の印刷会社が詳しく解説|角形封筒との違いもわかる
- 【完全保存版|角2封筒とは】A4対応サイズ・切手代・郵便料金・書き方・横書きマナーまで全網羅!2025年最新ガイド
- 長3封筒とは?サイズ・切手・書き方・重さまで完全ガイド|新潟の印刷会社がやさしく解説
- 宛名ズレ・透けを防ぐ!窓付き封筒の折り方・入れ方・注意点を完全ガイド
- 文明を動かした印刷革命|ヨハン・フストとグーテンベルクのすれ違い、そして未来へ【印刷の歴史】
- チラシとは何か?その歴史と力を新潟の印刷会社がドラマティックに解説
- ポスターとは何か?その歴史と力を新潟の印刷会社がドラマティックに解説
- 文明を支えた紙の歴史をドラマティックに解説。紙とは何か?|新潟の印刷会社がご紹介!
- グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

