新潟で「学校要覧」の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。
導入:学校要覧、毎年「どう作るか」に悩んでいませんか?
学校運営に欠かせない広報ツールの一つ、「学校要覧(がっこうようらん)」。
校長先生や教頭先生、または事務・広報担当の先生方のなかには、毎年この制作時期になると「去年のものを踏襲していいのか?」「今年の特色はどう表現しよう?」「ページ構成はこれで足りる?」と、悩みの声をあげる方も多いのではないでしょうか。
学校要覧とは、学校の理念・教育方針・沿革・学級数・教職員構成・行事予定・施設紹介などを網羅した、いわば**「学校の公式パンフレット」**です。
教育委員会への報告資料として、また学校説明会や地域との連携、保護者への理解促進、進学や転校希望者への情報提供など、さまざまな場面で活用される重要なドキュメントです。
しかしこの学校要覧、「決まったフォーマット」があるようでないのが実情。
全国共通の様式があるわけではなく、自治体や学校種別(小学校・中学校・高校・特別支援学校など)によって必要とされる項目や構成が少しずつ異なります。
さらに、印刷・製本の仕様やデザイン面、さらにはデジタル配布への対応も年々求められるようになってきました。
実際、
「今の学校要覧、内容が古くなってきたけどどこから手をつければいい?」
「PDFと冊子、両方作るにはどうすればいい?」
「地域の特色をもっと伝えたいが、見せ方が分からない」
といったご相談が多数寄せられています。
特に新潟県内では、少子化・学校統合・地域との連携強化などを背景に、学校の顔としての「要覧」の存在感が高まっていると感じています。
ただの報告書ではなく、「地域とつながる広報誌」「未来の児童・生徒を迎える学校の入り口」として、より戦略的な見せ方・届け方が求められているのです。
そこで本記事では、
-
学校要覧に必ず載せたい内容の一覧チェックリスト
-
ページ構成やデザインの考え方
-
印刷・製本仕様の選び方
-
スケジュールと進行管理のコツ
…など、**「学校要覧を一から作りたい」「今年はもっと良くしたい」**という担当者の方に向けて、実務に即した完全ガイドをご用意しました。
印刷会社目線の具体的なノウハウと、地域密着で教育機関を支えてきた経験をもとに、安心して進められる道しるべとしてお届けします。
次章から、実際に「学校要覧って何を載せればいいの?」という根本から、一緒に紐解いていきましょう。

第1章:学校要覧とは?その目的と役割【完全解説】
「学校要覧(がっこうようらん)」とは、学校の教育理念や運営方針、特色、教職員構成、生徒数、年間行事、施設など、学校の全体像を網羅的にまとめた広報資料です。
一言でいえば、**“学校の顔”**とも呼べる存在であり、教育委員会や地域社会、保護者、外部関係者に対して「この学校は、どのような想いで、どのような取り組みをしているのか」を伝えるための公式パンフレットです。
しかし、「要覧をどう作ればいいか分からない」「何を載せるのが正解なのか自信がない」という先生方の声を、数多く聞いてきました。
テンプレートがあるようでなく、前年の流用だけでは不安。でもゼロから作るのは骨が折れる…。
そんな現場のリアルな悩みにこたえるため、この章ではまず**「学校要覧の基本的な役割と意義」**を徹底解説します。
1. 学校要覧は“ただの資料”ではない。「信頼」を築くツール
学校要覧というと、「教育委員会に提出する堅い資料」「毎年なんとなく更新しているもの」といったイメージを持っている方もいるかもしれません。
しかし、それだけではもったいない!
学校要覧は、実は**「対外的な信頼構築ツール」**として、今もっとも注目されている広報媒体の一つなのです。
たとえば、保護者にとっては「どんな理念で教育しているか」「安全・安心に学べる環境があるか」「学力・人間力をどのように育てているか」を知る重要な判断材料になります。
進学・転校希望者にとっては、パンフレットとしての役割を果たし、学校選びの決定打になることもあります。
地域住民にとっては、「地域と共に育てている学校」の存在を感じてもらう入り口になります。
つまり学校要覧は、教育活動を社会に開き、**学校と地域・保護者・未来の子どもたちをつなぐ“架け橋”**でもあるのです。
2. 想定すべき“読み手”は多岐にわたる
学校要覧が届けられる相手は、意外と幅広いです。下記のように、複数の立場の人々が要覧を手に取ることになります:
-
教育委員会や行政関係者:監督・管理・報告資料として
-
保護者(在校生・新入生):学校説明会や入学案内に同封
-
地域住民や企業:学校行事や地域連携活動の案内を兼ねて
-
他校関係者・進学先の担当者:参考資料や交流資料として
-
転校希望者や新任教職員:学校理解のための基礎資料として
このように、読者は必ずしも“教育の専門家”とは限りません。
だからこそ、「誰が読んでも分かりやすい構成・ビジュアル・トーン」が不可欠なのです。
専門用語の使いすぎ、文字の詰め込みすぎ、古いレイアウトのままでは、せっかくの魅力が伝わりません。
3. 今どきの学校要覧には“伝える力”が求められる
最近では「学校のパンフレットを“ブランディング資料”として使いたい」というご要望が増えてきました。
たとえば:
-
英語教育に力を入れている → プログラムや実績をカラー写真付きで紹介
-
地域との交流が盛ん → 地元との連携事業やイベント実績を特集ページに
-
ICT教育・SDGsなど現代的なテーマ → インフォグラフィックで視覚的に整理
こうした「伝え方の工夫」は、まさに印刷会社の腕の見せ所。
写真や図表の使い方、レイアウト、色づかい、フォント選びひとつで、学校の雰囲気がガラリと伝わるようになります。
また最近では、デジタル配布との併用(PDF・学校サイト掲載など)も主流に。
紙の要覧をそのままPDF化するのではなく、“WEBでも読みやすい仕様”にデザインすることが求められます。
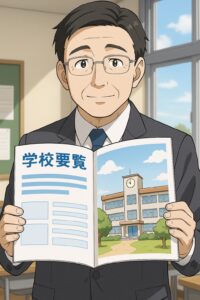
第2章:学校要覧に載せる内容一覧|チェックリスト付きでモレなく安心!
学校要覧を作るうえで、まず悩むのが「何を載せればいいのか?」という内容構成。
昨年のデータをそのまま流用…という手もありますが、それだけでは伝えたい情報が不足していたり、情報が古くなっていたりすることもしばしば。
そこでこの章では、学校要覧に必ず盛り込みたい項目をチェックリスト形式で一挙紹介します!
学校の特色・教育方針をきちんと伝えたい方も、教育委員会提出用に正確な構成をしたい方も、このリストがあれば安心です。
印刷会社としての立場から、「実際によく使われる構成」と「最近増えているトレンド情報」も交えて解説していきます。
基本構成【定番項目】
以下の情報は、ほぼすべての学校要覧に掲載されている“鉄板”項目です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 表紙 | 学校名、年度、校章、キャッチコピー(スローガン) |
| 学校概要 | 校名、所在地、電話番号、設立年、校長名 |
| 校長あいさつ | 教育理念や方針、地域への思いなど |
| 教育目標・学校目標 | 年度方針や重点目標などを明文化 |
| 校歌・校章の由来 | 校章のデザインや歌詞の意味など |
教育活動・組織編成
ここは学校の特色が表れる重要パート。教育方針とともに教育の“中身”を見える化しましょう。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 教職員構成 | 教員数、事務職員、養護教諭などの人数と配置 |
| 学級数・児童生徒数 | 学年ごとのクラス数、在籍人数、特別支援学級など |
| 年間行事予定 | 春・夏・秋・冬で主な行事を月別に記載 |
| 教育課程・特色教育 | 英語・プログラミング・農業・福祉教育などの特化領域 |
| 指導体制 | 補習体制、家庭学習サポート、外部講師の有無など |
実績・成果・評価
“成果を見せる”ことは信頼構築にもつながります。わかりやすく、具体的に。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 学力テスト結果 | 全国・県の平均との比較、推移グラフなど |
| 学校評価 | 学校関係者評価・自己評価・保護者アンケート等 |
| 表彰・受賞実績 | 個人・団体の表彰や大会成績など |
| 卒業後の進路 | 高校・大学進学実績、地元就職率など(高校) |
地域連携・生活環境
学校が“地域とともにある”姿勢を示す重要パート。信頼性アップの鍵になります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| PTA活動紹介 | 年間スケジュール、地域清掃やイベント支援など |
| 地域との連携事例 | 町内会・自治体・企業との共同活動 |
| ボランティア活動 | 高齢者施設訪問、防災訓練協力など |
| 学校施設の開放状況 | 体育館・校庭・図書室の地域利用情報など |
校内環境・施設・ICT設備
施設環境が整っているかは保護者が特に気にするポイント。写真付きでの紹介が効果的です!
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 校舎・施設紹介 | 教室・体育館・音楽室・図書館・家庭科室など |
| ICT環境 | タブレット導入状況、Wi-Fi整備状況、GIGAスクール構想対応など |
| 安全対策 | 校内見守りカメラ、登下校システム、防災備蓄など |
| 清掃・衛生環境 | トイレ改修、感染症対策、手洗い場の整備状況など |
補足・トレンド項目(今どきの学校要覧で増えている!)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| SDGsの取り組み | 環境学習、リサイクル活動、フードロス削減など |
| 不登校・支援対策 | 別室対応、相談窓口、スクールカウンセラー配置 |
| 外国籍児童対応 | 通訳支援、翻訳ツール活用、日本語指導体制 |
| SNS・広報活動 | 学校ブログ、SNS発信、写真掲載のルールなど |
【おまけ】こんな情報も意外と見られています!
-
給食の献立例(月1週間分などを写真つきで紹介)
-
卒業生の声・保護者インタビュー(地域との信頼感UP)
-
教育活動風景のフォトギャラリー(巻末に入れると効果大)
-
校内キャラクターやマスコット紹介(特別支援校で多い)
📝【校長挨拶 全5例文】
例文①:地域密着・伝統重視型
本校は昭和〇〇年に創立され、〇〇年の歴史を刻んできた伝統ある学校です。この長い年月の中で、地域の皆様、保護者の皆様、そして卒業生の皆様に支えられながら、多くの児童生徒がここで学び、育ち、社会へと巣立っていきました。
私たちは、「ふるさとに学び、ふるさとを愛する子どもを育てる」という言葉を教育の根幹に据え、日々の学びや行事、地域交流の機会を通して、子どもたちが自分の暮らす地域に誇りと愛着を持てるよう努めています。
小規模校ならではの温かな雰囲気と、教職員全員が子どもたち一人ひとりに目を配れる環境の中で、子どもたちは人とのつながりを大切にしながら、確かな学びと豊かな心を育んでいます。
また、地域との協働による環境学習や伝統文化の継承活動、世代間交流などを積極的に取り入れ、教室の中だけにとどまらない“生きた学び”を実現しています。
今後も、地域に根ざした学校づくりを継続し、子どもたちの未来を見据えた教育活動に取り組んでまいります。皆様方の引き続きのご支援とご協力を、心よりお願い申し上げます。
例文②:ICT・新教育対応型
本校では、「変化の時代をしなやかに生き抜く力を育てる」ことを教育の柱とし、子どもたちが自ら学び、考え、行動できる力を育む教育を実践しています。現代は、かつてないスピードで社会や技術が変化する時代です。そんな未来を生きる子どもたちには、知識を覚える力だけでなく、それを活用し、新しい価値を生み出す力が求められます。
本校では、ICT教育や探究学習、協働的な学びに力を入れ、タブレット端末やクラウド教材、デジタルホワイトボード等を活用した授業を日常的に行っています。学習の個別最適化と協働的な思考の育成を両立するため、教員も日々の授業改善に取り組み、互いに学び合いながら新しい教育の形を模索しています。
さらに、地域との連携やキャリア教育も充実させ、生徒が学校の中だけでは得られない“社会との接点”を持てるような取り組みを多数行っています。ボランティア、職場体験、地域課題に取り組む探究活動など、教室の外の学びにも重きを置いています。
今後も、保護者・地域・生徒と共に、新しい時代にふさわしい「共創型の学校づくり」を推進し、子どもたちの可能性を最大限に引き出す教育を行ってまいります。
例文③:未来志向・メッセージ重視型
本校が掲げる教育の原点は、「夢を描き、それを実現する力を育むこと」です。未来は、与えられるものではなく、自らの意志と行動によって切り拓いていくもの。私たちは、子どもたち一人ひとりが自分の人生の主人公として、自らの可能性に挑み続けられるような学びの場を創り出すことに日々努力しています。
現在、本校では探究学習を中心に、ICT・グローバル教育・プロジェクト型学習など、教科学習を越えた複合的な学びの仕組みを整備しています。生徒が自分の「好き」「やってみたい」「知りたい」から出発し、仲間と共に対話し、壁を乗り越えていくプロセスこそが、最も本質的な成長の源であると私たちは考えます。
教職員は“教える人”ではなく、“ともに学ぶ伴走者”として、生徒の挑戦と変化に寄り添い、時に背中を押し、時にそっと待つことを大切にしています。
教室、校舎、地域、社会、そして世界へ。学びの舞台はどんどん広がっています。私たちはこれからも、“変化を恐れず、共に未来を創る学校”として、挑戦を続けてまいります。
例文④:生徒主体・共育型
「ともに学び、ともに育つ」――これは本校が開校以来、大切にしてきた教育理念の一つです。私たちは、学校が知識を受け取る場ではなく、子どもたち自身が“学びの主人公”となり、教職員や仲間たちと関わりながら自ら成長していく“共育(きょういく)の場”であることを常に意識しています。
子どもたちは、日々の授業や学校生活の中で、さまざまな問いに出会い、それに向き合う過程で自分なりの考えや方法を見つけていきます。その過程を支えるのが、私たち教職員の役割です。ただ教えるのではなく、導き、支え、挑戦を見守る伴走者として、一人ひとりの歩みに寄り添っています。
生徒会活動やボランティア活動、地域連携の取り組みなど、教室を飛び出した実社会での学びも重視しています。社会の一員として自分の役割を自覚し、仲間と協働する経験は、知識だけでは得られない“生きた力”を育てます。
私たちは今後も、生徒たちの小さな気づきや挑戦を大切にし、学びの中に“自分らしさ”を見出せる学校づくりを進めてまいります。
例文⑤:共生・多様性重視型
本校は、「一人ひとりがかけがえのない存在である」という理念のもと、すべての児童生徒が安心して学び、成長できる共生社会の縮図となるような学校づくりを進めています。
多様な価値観、多様な背景、多様な特性を持った子どもたちが、互いを尊重し合いながら共に過ごす日々の中で、社会で本当に必要とされる「共感力」「対話力」「柔軟性」が育まれていくと私たちは信じています。
障がいや言語、文化、家庭の違いを壁ではなく「学びのチャンス」と捉え、私たちはそれぞれの子どもに応じた支援と環境整備を行っています。特別支援教育の充実、ユニバーサルデザインの推進、外国籍児童への多言語対応など、多様性を前提とした教育環境の構築に取り組んでいます。
また、日常的な対話や小さなふれあい、学校行事や地域交流の中で、「自分とは違う誰か」と共に在ることの価値を、子どもたち自身が自然と学べるよう工夫しています。
今後も、「誰ひとり取り残さない」学校づくりを目指し、すべての子どもたちの“ありのままの個性”が輝く教育を続けてまいります。
📝【教育目標・理念・指導方針 全5例文】
例文①:シンプル&具体型(小学校向け)
【教育目標】
○ よく考え、すすんで学ぶ子ども
○ 明るく、思いやりのある子ども
○ 健康で、心も体もたくましい子ども本校では、上記の三本柱を教育目標とし、すべての児童が心身ともに健やかに、そして人間らしく育っていけるよう、日々の教育活動に取り組んでいます。
「よく考える力」は、思考力・判断力・表現力の基礎であり、これからの社会で求められる“自ら学ぶ力”です。授業では対話や発問を大切にし、自分の考えを言葉にして伝える経験を積み重ねています。
「思いやりの心」は、人との関わりの中で育まれます。学級活動や異学年交流、地域行事への参加を通して、多様な他者と出会い、助け合い、支え合う心を育てています。
そして、「健やかな体と心」を育てるために、体育・食育・生活指導・保健活動に学校全体で取り組み、生活習慣や自己管理能力の向上を図っています。【めざす学校像】
○ 安心・安全で、すべての児童が毎日笑顔で登校できる学校
○ 個性が尊重され、得意なことを伸ばし合える学校
○ 家庭・地域・学校が協力し合い、信頼で結ばれた学校
例文②:中学校〜高校向け、文脈豊富型
【学校教育目標】
○ 主体的に学び、共に育ち、社会に貢献できる生徒の育成本校では、変化が激しく、予測困難な時代においても「確かな力をもって生き抜く人間」を育てることを教育の中心に据えています。学びに対する主体性と、周囲との共生意識、そして社会との接点を持つ姿勢を育むことが、教育の目的であると考えています。
【育てたい生徒像】
○ 知識を活用し、自ら課題を見つけて解決できる生徒
○ 他者と協働し、多様性を理解・尊重する姿勢を持つ生徒
○ 地域・社会・世界に関心を持ち、自分の役割を見出せる生徒【指導方針】
授業改善を核とした学力の定着と伸長
道徳・キャリア・総合的学習の時間を通じた心の育成
生徒指導・生活指導の徹底による規律ある校風づくり
ICTの活用による個別最適な学びと協働的な学びの融合
地域社会・保護者・卒業生とのつながりを活かしながら、「学びの共同体」としての学校づくりを進めています。
例文③:理念・ビジョン重視型(校長メッセージ型)
【スクールビジョン】
○ 子どもたち一人ひとりが「学びの主人公」になる学校
○ 自分の可能性に挑戦し、“夢の種”を育てられる学校
○ 教職員と地域がともに子どもを育てる共創の学び舎本校では、「教育とは未来をつくる営みである」との理念のもと、単なる知識伝達ではなく、“子どもたち自身の人生を拓く力”を育む教育をめざしています。
学力・体力・心のバランスのとれた育成を目指すとともに、「どう学ぶか」「何を感じるか」「どんな社会を目指したいか」といった“学びの意味づけ”を大切にしています。【育てたい生徒像】
○ 自ら問いを持ち、探究し、成果を社会に還元できる生徒
○ 多様な人と協働し、相手を思いやれる人間性を持つ生徒
○ 自分と社会との接点を理解し、行動に移せる責任ある市民教職員一人ひとりが「子どもたちの未来に責任を持つ存在」としての自覚を持ち、日々実践と対話を重ねています。
例文④:キャリア教育重視型
【教育目標】
○ 将来を見据え、自ら進路を切り拓く力を持つ生徒の育成【キャリアビジョン】
本校では、キャリア教育を“教科の枠を越えた人間形成の根幹”と位置づけ、学年ごとに体系的な指導計画を構築しています。
自己理解から職業理解、さらには社会課題への関心・行動へと段階的に視野を広げていくカリキュラムを設けています。
生徒は、インターンシップ・進路ガイダンス・模擬面接・職業調べ・地域人材との対話など、実践的なプログラムを通じて、“社会と自分のつながり”を意識するようになります。【育てたい生徒像】
○ 自分の将来に主体的に向き合い、行動計画を立てられる生徒
○ 働く意味・生きる意味について考え、自分なりの価値観を育てられる生徒
○ 周囲の支えに感謝し、未来を社会に還元しようとするマインドを持つ生徒「進路指導ではなく、“人生支援”としての教育を」――それが本校のキャリア教育のあり方です。
例文⑤:環境・SDGs・地域共創型
【教育目標】
○ 地域と世界を見つめ、持続可能な未来をともにつくる児童生徒の育成【理念】
本校では、地域環境や文化、経済、人とのつながりなど、身近な生活の中にこそ「地球規模の学び」があると考えています。
総合的な学習や探究の時間を中心に、地域資源を活用した学習、ゴミ問題・エネルギー・食品ロス・ジェンダー・貧困など、SDGsの視点から社会課題を自分ごととして捉える学習に力を入れています。【育てたい児童生徒像】
○ 観察・調査・対話を通じて地域や自然に関心を持ち、持続可能性の視点で行動できる子ども
○ 仲間とともに課題を発見・分析し、アイデアを出し合い、行動できる協働型リーダー
○ 世界を自分の言葉で語れる、多様性と共生を大切にする市民学校という枠を超え、地域とともに学び、社会とつながる「開かれた学びの場」としての学校づくりを進めています。
第3章:学校要覧のページ構成とデザインのポイント|“伝わる冊子”にするために
学校要覧は、単に情報を詰め込むだけではもったいない!
どれだけ素晴らしい教育方針や地域連携の取り組みがあっても、「伝わる形」に整っていないと魅力は半減してしまいます。
ここでは、読者の目線に立ち、「見やすい」「分かりやすい」「読みたくなる」要覧を作るための構成設計・デザインの極意を解説します。
さらに、実際に制作現場でご提案しているレイアウト実例やトレンドの表現手法も盛り込んでいます!
1. ページ構成の基本は「4の倍数」!でも正解はひとつじゃない
冊子印刷は「中綴じ」や「無線綴じ」が主流のため、基本的にページ数は**4の倍数(8P・12P・16Pなど)**で構成します。
無理に増やす必要はありませんが、「詰め込みすぎて見づらい」「余白がなく読みにくい」などの事態を避けるためにも、読み手目線で適正ページ数を決めることが大切です。
ページ数別の特徴とおすすめ構成例:
| ページ数 | 向いている学校 | 特徴 |
|---|---|---|
| 4P構成(両観音開き) | 小規模校/保育園/簡易版 | 情報を厳選してスッキリ見せる |
| 8P構成(中綴じ) | 一般的な公立小・中学校 | 情報量と見やすさのバランスが◎ |
| 12P構成 | 高校/特色教育の多い学校 | 教育内容・施設・行事などをしっかり紹介 |
| 16P以上 | 私立校/専門性の高い学校 | 写真やグラフを多用、ブランド冊子化も可能 |
2. セクションごとの「流れ」が大事!読者が迷わない構成を意識
構成の順番にも意図があります。基本は「導入 → 教育内容 → 実績 → 地域・生活環境 → 巻末情報」の流れが自然で読みやすいです。
おすすめセクション構成例(8Pの場合):
-
表紙(校名、年度、ビジュアル写真、スローガン)
-
校長挨拶/学校概要
-
教育目標・理念・指導方針
-
教職員体制・学級数・生徒数
-
教育課程/特色教育/ICT・SDGs紹介
-
年間行事/学校評価/実績紹介
-
地域連携/PTA活動/施設紹介
-
巻末:校歌・校章・アクセス/裏表紙(お問い合わせ)
※中綴じ冊子の場合、4・5ページ中央は見開き構成にして、行事カレンダーや施設MAPを大きく載せると効果的!
3. デザインの工夫次第で、“伝わる”学校要覧に
【1】フォント選びのコツ
-
見出しにはゴシック系(太め)でメリハリを。
-
本文はUDフォント(ユニバーサルデザイン)推奨。読みやすく、誤読防止にも有効。
-
小学校では漢字にふりがなを振るケースもあり。
【2】配色と余白のバランス
-
学校カラーをベースに、清潔感のある白地や淡色で統一感を。
-
“余白”は大事。情報を詰めすぎないことで視線誘導がスムーズに。
-
ポイントカラーでグラフや見出しを目立たせると◎。
【3】写真・図表の活用
-
児童・生徒の表情が見える写真は強い説得力を持つ(※肖像権・同意に注意)。
-
年間行事や成績推移は、グラフやアイコン付きの図表で視覚化すると理解が進む。
-
フォトギャラリー風レイアウトで楽しい印象を加えるのも効果的。
4. よくあるNG例と改善ポイント
| NG例 | 改善提案 |
|---|---|
| 情報が文字だらけで読む気がしない | 写真・図表を使って「視覚情報」に変換 |
| ページの情報量に差がありすぎる | 内容を再構成し、均等に配置する |
| 配色がちぐはぐで読みにくい | 学校カラー+補色の2〜3色で統一感を |
| 保護者・地域に向けた視点が弱い | 子ども中心・家庭とのつながりも意識して記載 |
第4章:学校要覧の印刷・製本仕様はこう決める!|見た目・コスト・使い勝手を全て両立
「ページ構成が決まった!デザインも整ってきた!」
――となると、次に考えるのが印刷と製本の仕様です。
印刷仕様は、見た目・耐久性・コスト・配布シーンに直結するとても大事な設計ポイント。
ちょっとした用紙の選び方、綴じ方の違い、紙厚の調整で、「読む気になるパンフレット」になるか、「読まれずに終わる冊子」になるかが分かれてきます。
この章では、教育現場にマッチする学校要覧の仕様選定について、実際の事例とともに解説します。
1. サイズは「A4」一択!理由は“わかりやすさと格納性”
学校要覧のサイズは、ほぼすべての学校が**A4サイズ(210×297mm)**を採用しています。
なぜA4が選ばれるのか?
-
学校の書類はほとんどA4で統一されているため、他の資料と一緒に保管しやすい
-
保護者に配布する際にも、クリアファイルに入れて渡せる
-
A4は閲覧性・レイアウトの自由度が高く、写真も文章も無理なく配置できる
-
両面印刷時の設計も想定しやすく、無駄が出にくい
※中にはB5判や正方形変形などの例もありますが、「見やすさ」「刷りやすさ」「保管しやすさ」を総合すると、A4が鉄板です。
2. 製本は「中綴じ」 or「無線綴じ」どっちがいい?
製本方法の選び方は、ページ数・印刷部数・配布用途によって変わります。
| 製本方式 | 特徴 | 向いている学校・状況 |
|---|---|---|
| 中綴じ(ホチキス留め) | 一般的/コスト◎/8〜16Pに最適 | 小中学校の定番/行事パンフ系 |
| 無線綴じ(糊で背を固める) | 高級感/多ページ対応/背表紙が作れる | 高校・私立・進学案内向け |
| 穴あけ+バインダー式 | 差し替えやすい/再編集に便利 | 年度ごとに一部情報更新する場合 |
おすすめ:8〜12ページであれば中綴じ。
しっかりした冊子感を出したい or 16ページ以上になる場合は、無線綴じにすると安心&かっこいい!
3. 用紙選びで見た目と質感を決める
表紙用紙(カバーに使う紙)
| 用紙 | 特徴 | 推奨厚さ |
|---|---|---|
| マットコート紙 | 落ち着いた質感/写真映え◎ | 135kg〜180kg |
| コート紙 | ツヤあり/鮮やか発色 | 135kg〜180kg |
| 上質紙 | 落ち着いた印象/筆記性あり | 135kg〜160kg |
学校要覧では「マットコート紙135kg」が最も人気。
「品がある」「ツヤが控えめで読みやすい」「写真映えしやすい」と三拍子揃っており、教育機関向けには理想的です。
本文用紙(中のページ)
| 用紙 | 特徴 | 推奨厚さ |
|---|---|---|
| 上質紙 | 白くて読みやすい/筆記しやすい | 90kg or 110kg |
| マットコート紙 | しっとり見せたい/写真もくっきり | 90kg〜110kg |
| コート紙 | 色がパキッと出る/カラーページが多いなら | 90kg |
おすすめ構成:表紙=マットコート135kg、本文=上質90kg。
これで“見た目の質感”と“読みやすさ”が両立できます。
4. 印刷方法の選び方|オフセット or デジタル?
| 印刷方法 | 特徴 | 向いている部数 |
|---|---|---|
| オフセット印刷 | 高品質・大量印刷向き/単価が安くなる | 200部〜数千部 |
| デジタル印刷 | 小ロット対応・短納期OK/版代不要 | 〜200部程度 |
-
500部以上 → オフセット印刷が断然お得&高品質
-
100部前後 → デジタル印刷でも十分キレイ
5. その他オプション|ちょっとの工夫でグレードUP!
| オプション | 内容 | おすすめ活用シーン |
|---|---|---|
| 表紙ラミネート | 光沢 or マットフィルムで耐久性UP | 再利用する資料/回覧資料 |
| 折り加工 | 三つ折り、Z折り、観音開きなど | 簡易要覧/配布用サマリー |
| ポケット付き冊子 | 中にプリントや名刺を挟める | 学校説明会で資料配布 |
こうしたオプションを活用することで、より「読まれる」「長く使われる」要覧に仕上がります。
第5章:作成スケジュールと制作の流れ|遅れない&失敗しない要覧づくりの秘訣
学校要覧の作成は、思っている以上に時間がかかるものです。
文章の原稿を揃えたり、写真を撮影・整理したり、内容の確認や校正を経てようやく印刷・製本へ…。
しかも、教職員の皆さんは本業(授業・会議・行事準備など)と並行して作業を進めることになります。
だからこそ、「とにかく早めの準備」と「段取りの見える化」が成功の鍵!
この章では、年度初めにスタートして、6〜7月納品を目指す想定で、スムーズに進めるためのスケジュールと制作フローを徹底解説します。
1. 学校要覧の制作スケジュール【基本型】
例:4月スタート → 6月下旬納品パターン
| 月 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 4月上旬 | 昨年度版の確認/修正点の洗い出し/制作チーム決定 |
| 4月中旬 | 掲載内容の整理・原稿作成スタート/必要写真の撮影開始 |
| 5月上旬 | 初稿原稿の提出/レイアウト案のすり合わせ |
| 5月中旬 | 校正1回目(誤字脱字・写真差し替え等) |
| 6月上旬 | 校正2回目/最終調整・校了(印刷OKの合図) |
| 6月中旬〜下旬 | 印刷・製本/納品完了・配布準備 |
※納品日は、学校説明会・教育委員会への報告日などに間に合うよう逆算するのが鉄則!
2. 具体的な制作フローと各ステップのポイント
【STEP 1】内容の確認・方向性決定(4月上旬〜中旬)
-
昨年の要覧をベースに「今年は何を変えるか?」を検討
-
今年度の教職員配置、学校目標の改訂有無を確認
-
写真撮影スケジュール(行事・授業風景など)もこの時期に計画
→ ここでの「準備力」が7割を決める!
【STEP 2】原稿の収集・編集(4月中旬〜5月上旬)
-
校長挨拶、教育目標、行事予定などを関係者から提出してもらう
-
写真も“使えるデータ”として収集(ピント・明るさ・肖像権OKかも確認)
-
学年ごとの特色紹介などもここで加筆する
→ WordやExcelでOK!印刷会社がDTPデータに変換可能
【STEP 3】デザイン制作・初校(5月上旬〜中旬)
-
提出原稿・写真をもとに印刷会社が**初校(1回目のレイアウト案)**を制作
-
見た目・構成・ページ順などの大枠をこの段階で決定
-
配色やフォントも希望があればこの時点で伝えると◎
第6章:学校要覧をもっと活かすアイデア集|“つくって終わり”にしないために
「学校要覧は教育委員会に提出するだけの資料」
そう思っていませんか?
確かに形式的には“報告書”ですが、実はそのポテンシャルはパンフレット、広報誌、ブランディングツール、説明資料…と、何通りにも活かせるのです。
この章では、せっかく時間と予算をかけて作る学校要覧を、「もっと見てもらえる」「もっと活用できる」アイデアをご紹介します!
1. 学校説明会・見学会で「入学パンフ」として活用
中学校・高校・特別支援学校ではもちろん、小学校でも増えているのが、学校説明会・オープンスクールでの配布。
来校者の手に渡る資料として、「理念・特色・教育の雰囲気」を伝えるのに最適です。
活用例:
-
学校要覧の内容をベースにした「簡易版パンフレット」を作る
-
フォトギャラリーやQ&Aを加えて、より読みやすく再構成
-
表紙に「〇〇年度 入学希望者向け」と追記するだけでも効果大!
2. PDF化して、学校ホームページや教育委員会サイトに掲載
紙で配るだけじゃもったいない!
今はデジタルでも閲覧できる形式にしておくのが常識です。
PDF配布のメリット:
-
保護者がスマホで手軽に閲覧できる
-
転入学希望者が事前に学校の様子を知ることができる
-
学校外からの問い合わせにもスムーズに対応可能
-
ペーパーレスで環境配慮/コスト削減にもつながる
※PDF化する際は、印刷データをそのまま流用せず、スマホやタブレットでも見やすいレイアウトを意識するのがポイントです!
3. 差し替え自由な「バインダー式」や「ポケット付き冊子」にして拡張性アップ
固定の冊子だけでなく、ページの追加・差し替えができる形態もおすすめです。
活用アイデア:
-
「基礎情報(校長挨拶・校章由来など)」は冊子で作成
-
「毎年更新が必要なデータ(職員数・成績・行事予定)」は、A4単ページで差し替え可能に
-
ポケットフォルダーに封入する形式なら、追加プリントや配布資料を同時に渡せる
→ 長期的に使えるツールとして価値が高まります!
4. PTA・地域との共有で“開かれた学校づくり”に活かす
学校要覧は、「地域の方々に学校を知ってもらう」絶好のツールです。
活用例:
-
地域行事・祭り・清掃活動時に配布(学校活動の信頼感UP)
-
学童保育・保育園連携・町内会での配布もアリ
-
PTAや地域ボランティアと「一緒に作るスタイル」も効果的
→ 教育委員会向け+地域向けの**“二面性を持った冊子”**という発想が新しい!
5. 卒業アルバムのサブツールとして活用する
ユニークな使い方として、学校要覧を卒業アルバムの資料編として使う学校も増えています。
-
「この年、学校はこうだった」という記録性
-
学級数・先生の一覧・行事予定が1冊に残る
-
未来の自分が“学校の空気”を振り返る資料として活用可能
→ 予備印刷で少し多めに作って、希望者に有償頒布するパターンも◎
6. 冊子以外の“広報グッズ”として派生展開する
学校要覧のデザインをもとに、以下のような広報物に展開することも可能です:
| グッズ | 活用シーン |
|---|---|
| リーフレット(3つ折り) | 説明会/PTA配布用の簡易版として |
| ポスター・掲示物 | 校内掲示/地域センターに設置 |
| SNSバナー画像 | Facebook、Instagram等のアイキャッチに |
| 校章ステッカー・封筒 | 学校郵送物に一体感を出す |
まとめ:学校要覧は“万能ツール”。活かし方しだいで効果10倍!
学校要覧は単なる提出用資料にとどまらず、「学校の想いを伝える」「地域との信頼を深める」「保護者に安心感を与える」ための**“教育広報ツール”**として活用できます。
デザインや仕様、活用方法まで一貫して考えることで、予算以上の価値を生む1冊になります!
【まとめ】学校要覧は、教育と地域をつなぐ「信頼の1冊」
新潟フレキソは、印刷だけじゃなく、“学校の想いを届ける”ためのパートナーです。
毎年の制作が少しでもラクに、そして学校の魅力をもっと伝えられるように。
先生方と同じ目線で、一緒に形にしていきます。
新潟市の印刷会社「株式会社新潟フレキソ」では、地域の学校さま向けに、学校だより・卒業文集・PTA広報誌・学校要覧などの印刷を幅広くサポートしております。
地元密着の印刷会社として、先生方の「困った」をいつでもお手伝いできるよう心がけております。
まずは、どんな些細なことでも構いません。
お気軽にご相談ください!
▶ 会社概要はこちら
▼関連記事はこちらから
- 教科書体とは?特徴・歴史・使い道を徹底解説|明朝体やゴシックとの違いも紹介
- 学校だよりの作り方・完全ガイド|新潟の印刷会社が広報・文例・配布・デザイン・印刷も徹底サポート!
- 【保存版|全60文例+挨拶ネタ240選】園だより・保育園だより・学校だより完全ガイド|4月〜3月・1年分まるごと対応!
- PTA広報誌の作り方 完全ガイド|新潟市の印刷会社が教える編集・構成・原稿文例・チェックリスト付き
- 紙って何でできてるの?家にある紙を5種類に分けて調べてみた|簡単!夏休みの自由研究にもおすすめ!新潟の印刷会社ブログ
- 【新潟の印刷会社が解説】防災訓練・地域活動で役立つ印刷物一覧|チェックリスト付きで実務にも安心
- 回覧板で配布するお知らせやチラシ作成のポイントを解説
- チョークと黒板の歴史と作り方|成分・色の理由まで徹底解説
- 地域をつなぐ!コミュニティ協議会広報誌の作り方【完全ガイド】|新潟フレキソが応援します!

