第1章:山の日っていつ?何のための日?
「え、山の日って祝日だったの?」
そう驚く人も、まだ意外と多いのかもしれません。
それもそのはず、山の日は2016年に施行されたばかりの“新しい祝日”。比較的新しいため、まだ世間での定着度は海の日や体育の日ほどではありません。
でも、なぜ山に感謝する日が必要だったのでしょうか?
なぜ8月11日という微妙な日付なのか?
いきなり山に登るわけでもないのに、「山の日」と言われてもピンとこない…というのが正直なところかもしれません。
しかし実は、この祝日には日本人の心と自然との関係をもう一度見つめ直すという、大きなテーマが込められているのです。
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」
これが、山の日に込められた正式な理念です。
日本は国土の約70%が山地。水・空気・木材・生態系──日々の暮らしは、知らず知らずのうちに山からの恵みに支えられています。
でも、都市化が進む中で、「山に親しむ」という文化はどこか遠ざかりつつあります。
かつては山を歩き、木を拾い、神を感じていたはずなのに──
私たちはその原点を忘れつつあるのではないか?
そんな問いかけが、この祝日に込められています。
そして、気になるのがこの問い:
なぜ「8月11日」なの?
「山」という漢字が「八」と「十一」に見えるから──
そんな話を耳にしたことがあるかもしれません。
でも、それって本当に理由になる?
実はその裏には、もっと深い事情があるのです…。
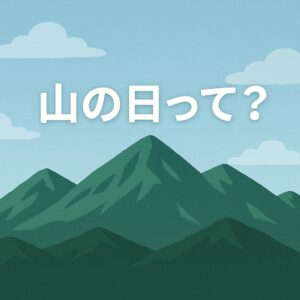
第2章:山の日はなぜ作られた?本当の背景とは
「海の日があるのに、山の日がないのは変じゃない?」
そんな素朴な疑問が、やがて国を動かす運動へと広がっていきました。
1996年に「海の日」が祝日として誕生したことで、自然をテーマにした記念日の存在意義が見直されました。山岳関係者や自然保護団体の中で、次第に「山にも感謝を示す日が必要だ」という声が高まっていったのです。
山岳団体の長年の想い
中心となったのは、日本山岳会をはじめとする登山・自然保護団体。
「山の日を作ろう!」という運動は、2000年代初頭からじわじわと広がり、2008年には“山の日制定議員連盟”が発足。
登山文化の啓発や自然への感謝の気持ちを伝えるため、官民が一体となった活動が続けられました。
ところが、祝日を1日増やすというのは、政治的にも経済的にも一筋縄ではいかないテーマ。
「経済が止まる」「生産性が下がる」などの反対意見も多く、調整は難航しました。
それでも実現できたのはなぜ?
実は、「山の日」にはもう一つの大きな背景があります。
それは──日本人の“自然との距離”が急速に広がっているという危機感。
都市化、IT化、便利な生活。
気がつけば、子どもたちは“山”に触れることなく成長し、大人たちも自然からの恩恵を意識する機会が減っていきました。
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」
この祝日の理念は、“自然と人の距離”を再び近づけるためのメッセージでもあるのです。
観光業・地域経済への期待も
夏は登山やキャンプが盛んなシーズン。
「山の日」を作ることで、山岳地域の観光活性化も期待されました。
特に地方では、登山者の来訪や山フェス、イベントなどを通じて地域振興につながるケースも増加。
このように、山の日は文化的・教育的・経済的な複合的な思惑の中から誕生したのです。
第3章:なぜ8月11日?語呂合わせだけじゃない本当の理由
「山の日は8月11日。なぜこの日?」
もっとも多く検索されているのが、この素朴な疑問です。
確かに、カレンダー的に微妙な位置。お盆にはちょっと早いし、明確な記念日でもない。
なぜこの日になったのか…実はそこには建前と本音、両方の理由が隠されているのです。
建前:漢字の形が「八=山のふもと」「十一=山の頂」
まず、よく語られるのがこの話。
「山」という漢字は、「八」と「十一」に分解できるように見える。
──つまり、「8月11日=山の日」は**語呂合わせ的にピッタリ!**という説です。
この話、実際に決定後にあちこちで広められましたが、
結論から言えばこれは**“後付け”の説明**にすぎません。
もちろんインパクトはありますが、これだけで祝日を制定するのはさすがに無理があります。
では、本当の理由は何か?
本音:お盆休みに連携しやすい“絶妙な日”
政府・自治体・経済界の意見を調整する中で、
**「お盆休みに近く、連休を取りやすい時期」**という実用的な観点が重視されました。
8月11日なら、企業や学校が12日に休みを取れば、
土日とあわせて**大型連休(山の日→お盆)**に繋がるケースが多くなる。
つまり、観光業や地域経済にとってもありがたい日程だったのです。
「山の日=自然への感謝」だけでなく、“経済効果”も見込める位置づけとして設定されたわけです。
幻の候補日「8月12日」を避けた理由
実は、当初は「8月12日」が有力候補でした。
ところが──
1985年8月12日、日本航空123便の墜落事故が発生。
群馬県の山中に墜落し、520人が犠牲になった、日本の航空史上最悪の悲劇です。
「山の日」という名の祝日を、事故があった“山の日”に重ねることへの配慮から、
候補日は1日繰り上げて8月11日へ変更されました。
この判断は、遺族や世論への敬意を払ったとても重要な背景だったのです。
「語呂」と「配慮」と「連休効果」
こうして「山の日」は、
-
覚えやすい語呂合わせ
-
社会的配慮(8/12回避)
-
経済的な効果(お盆前)
という3つの視点が重なった**“絶妙な日”**として生まれました。
単なる記号のような日付にも、実はこうした深いストーリーが隠されているのです。
第4章:山は、昔から日本人の心のよりどころだった
「山を見ると、なんだか落ち着く」
そんな気持ちになったことはありませんか?
それもそのはず──日本人にとって“山”は、ただの地形ではなく、心のよりどころだったのです。
山は、自然の象徴であり、祈りの場であり、ときに“神”そのものでした。
山=神のすみか
古代の日本では、山は“神が宿る場所”とされていました。
「山岳信仰」と呼ばれる文化は、全国各地に根付いています。
-
富士山:霊峰として信仰の対象に。古来より修験道や登拝が行われてきた。
-
白山、立山、出羽三山:それぞれが“死と再生”“生と死の間”を象徴する聖地。
-
山頂に神社がある山は全国に数多く、「登ること=神に近づくこと」とされた。
山の静けさ、厳しさ、圧倒的な存在感。
それらは、畏敬(いけい)と信仰の心を自然に生み出していたのです。
山と暮らしの一体感|“里山文化”
神だけではありません。
山は私たちの暮らしのすぐ隣にありました。
-
山菜、きのこ、薪、木材、動物──日々の糧をもたらす恵みの源。
-
斜面を活かした棚田、山の水を利用した農業。
-
山の斜面に沿った集落と、その風土に根ざした生活様式。
これらは「里山文化」と呼ばれ、自然と人間が無理なく共存してきた証です。
その関係は、現代のように“自然を守る”“自然を利用する”という二項対立ではありませんでした。
一緒に生きる、という感覚があったのです。
“現代人”にとっての山とは?
そして今。
都会に住む私たちは、日常の中で山を意識する機会が減ってしまいました。
けれど──
-
登山で汗をかいたときの達成感
-
山の空気を吸い込んだときの安心感
-
遠くに見える山のシルエットに、なぜか心を奪われる感覚
それらは、太古から続く“山と人の結びつき”が今も生きている証拠ではないでしょうか。
「山の日」は、そんな山とのつながりを、もう一度思い出すためのきっかけです。
山に登らなくても、遠くから見つめるだけでもいい。
大切なのは、“自然に想いを寄せる”という心の姿勢なのです。
第5章:山の日の過ごし方いろいろ|登らない人にもできること
「山の日って、やっぱり登山しなきゃダメ?」
──そんなことはありません。
たしかに、山に登るのは王道の楽しみ方。
でも、山に行かなくても、山を感じることはできるんです。
山の日は“強制的なイベント”ではなく、自然と向き合うチャンスなのです。
アイデア1:近くの丘、公園、小さな山でOK
大きな登山計画を立てなくても、
・地元の低山ハイキング
・近所の高台から景色を見る
・森林公園や里山を散歩する
──こんな小さな自然体験でも、心がほっと緩みます。
「登った先の景色」ではなく、
「自然の音、におい、静けさ」を楽しむだけでも立派な“山時間”です。
アイデア2:山にまつわる映画や本を楽しむ
例えば──
・『岳』『エベレスト』『Into the Wild』などの山映画
・登山エッセイや自然エッセイを読む
・山岳写真集を眺めるだけでも気持ちは山の中
ソファに座っていても、心は頂上へ。
“山を感じる”のに、場所は関係ありません。
アイデア3:山をテーマにしたTシャツや雑貨で気分を上げる
気軽に“自然モード”に入るなら、
・山モチーフのTシャツ
・登山部っぽいロゴの帽子
・アウトドア系のグッズでコーデを楽しむ
実はこの「気持ちのスイッチ」がとても大事。
心に自然を取り入れることで、ふだんの生活も少し優しくなります。
アイデア4:子どもと一緒に“山のこと”を話してみる
「山って何があるんだろう?」
「どうして水が流れてくるの?」
そんな問いかけから、自然への関心が芽生えることも。
実際に登らなくても、“山の恵みを意識する”ことが教育の第一歩になります。
アイデア5:“静かに感謝する”だけでもいい
山の恵み──
水、木、空気、風景、文化、神話、食べもの。
それを少しだけ思い出すだけでいい。
自然を意識する、その「心の動き」こそが、山の日の本質かもしれません。
第6章:山に行く人も、行かない人も。“自然をまとう”って、ちょっといい
山の空気、森のにおい、木漏れ日。
そんな自然の感覚を、日常に持ち帰ることができたら──
それを叶える、ちょっと素敵な方法があります。
それが「自然をまとうTシャツ」。
ORiJi!の“山T”で、気分はいつでもアウトドア
新潟のオリジナルTシャツ屋 **ORiJi!(オリジー)**では、
自然や山をテーマにしたデザインTシャツも制作できます。
-
登山サークルのオリジナルTシャツ
-
アウトドア好き仲間との“山ガール”Tシャツ
-
家族で着られる「ゆるキャン風」デザイン
-
ソロキャンパー向け“静かな山”系アートTシャツ
1枚からOK。
素材も吸汗速乾・UVカットなど、アウトドア仕様のTシャツボディも選べます。


記念日にも、旅のおみやげにも。
「山の日に初登頂できた記念」
「毎年恒例のキャンプの思い出に」
「自然が好きなあの人へのプレゼントに」
Tシャツは“思い出を形にする”アイテムでもあります。
お気に入りの山の名前、標高、登頂日を入れるのもおすすめ!
小ロットOK!手描きのイラストもプリントできる
ORiJi!なら、
・スマホのスケッチ
・子どもの描いた山の絵
・趣味で描いたイラストデータ などもそのままTシャツにできます。
「山の日の想い出」が、
世界に一つのアイテムとして、手元に残せるのです。
→ オリジナルTシャツ制作ページはこちら
制作事例はInstagramでも随時更新中!
第7章:まとめ|山の日は、静かに自然を思い出すチャンス
山に登らなくてもいい。
自然にいるわけじゃなくてもいい。
大切なのは、ただ「思い出す」こと。
「自分は自然の一部だったんだ」
「水も木も空気も、ぜんぶ“誰か”のおかげだったんだ」
──そんな気づきが、ほんの一瞬でも心をよぎれば、それだけで山の日は意味のある一日になります。
山は、私たちを見下ろす存在ではなく、
いつも少し離れたところから、静かに寄り添ってくれている存在なのかもしれません。
遠くからでも、心のなかで手を合わせることはできる。
だからこそ山の日は、登る人も、登らない人も、**誰もが参加できる“優しい祝日”**なのです。
そしてその気持ちを、Tシャツという形で残してみるのも、ひとつの方法です。
-
思い出の風景を描いたTシャツ
-
山仲間とおそろいのロゴ入りウェア
-
子どもの描いた“マイ・マウンテン”をプリントした1枚
**ORiJi!(オリジー)**では、そんな「想いのこもった服作り」を全力でお手伝いしています。
山の日の記念に、あなたの自然愛を形にしてみませんか?

📝コラム:山の日・海の日は祝日なのに…「川の日」ってあるの?
「山の日」「海の日」と聞くと、ピンとくる人は多いはず。
カレンダーにしっかり書いてある国民の祝日で、夏のイベントとも相性バッチリ。
じゃあふと思いませんか?
「川の日」って、あるの?
あっても良さそうじゃない?
実は──あります。
でも、ちょっと“扱い”が違うんです。
■ 川の日は「7月7日」──でも祝日じゃない!
「川の日」は、1996年に旧・建設省が制定した記念日。
日付は7月7日。
そう、七夕=天の川にちなんで選ばれた、ちょっとロマンチックな記念日です。
この日を通して、
「川に親しみ、川の恵みに感謝し、水辺の大切さを学ぼう」
という意図が込められています。
ですが……これはあくまで**「記念日」**。
「国民の祝日」ではないため、カレンダーにも載っておらず、知らない人も多いのが現状です。
■ なぜ祝日にならなかったのか?
理由はいくつかあります。
-
7月中旬にはすでに「海の日」があり、スケジュール的に混雑していた
-
「山」や「海」は象徴性が強く、祝日としてイメージしやすかった
-
川は全国どこにでもあるぶん、“特別感”を出しづらかった
-
祝日を1日増やすには、法改正や国民的な支持が必要だった
実際、「川の日」を祝日化しようという動きは一部あったものの、広く盛り上がるには至りませんでした。
■ それでも「川の日」は、静かに続いている
たとえ祝日でなくても、「川の日」はちゃんと毎年存在しています。
-
各地の河川で清掃活動
-
子ども向けの水辺学習、川遊び体験
-
防災・水害への備えを学ぶイベント
-
「水の週間」(7月1日〜7日)と連動したキャンペーン
地味かもしれない。
けれど、暮らしに最も近い自然が「川」なのかもしれません。
■ 山・海・川──三つそろって、やっと“自然”
祝日になったから偉い、というわけではありません。
むしろ「川の日」が祝日にならなかったことで、こう問いかけてきます。
あなたは、川のことを忘れていませんか?
山の頂、海の広さ、そして川のせせらぎ。
それぞれ違うけれど、どれも私たちの命を支えている自然の一部。
“自然と親しむ日”がカレンダーにあってもなくても、
心の中に「川の日」を持っていたいものです。
ORiJi!(オリジー)は株式会社新潟フレキソが運営する新潟市を拠点とするオリジナルTシャツ作成販売店です。
下記よりお気軽にお問い合わせください。
関連記事
■新潟でクラスTシャツを作成するならORiJi!(オリジー)で!【ご注文の流れ】
■キャンプ好き必見!新潟でキャンプグッズを作るならORiJi!|Tシャツ・ステッカー・用品まとめ
■のぼり旗とは?用途・素材・サイズ・設置方法まで完全ガイド【初心者必見】
■DTFプリントとは?新潟のオリジナルプリントTシャツ屋ORiJi!が解説するそのメリットと活用法
■5月30日は「ごみゼロの日」|由来・意味・環境への想いをやさしく解説【何の日?】Tシャツも作ってみた。|新潟のTシャツ屋
■今日は何の日?6月4日は虫の日|由来と意味&記念Tシャツで祝ってみた!【新潟のTシャツ屋ORiJi!(オリジー)】
■海の日はなぜ祝日?実は深い由来と想いがあった…その気持ち、Tシャツにしよう|新潟ORiJi!

