1.はじめに:地域に欠かせない「コミュニティ協議会広報誌」とは?
地域を支える――それは、決して大げさな言葉ではありません。
私たちが暮らす町、地区、地域社会。そこには、目には見えにくいけれど確かな「つながり」があります。
そのつながりを育み、支えているのが、コミュニティ協議会です。
そして、そんなコミュニティ協議会にとって、欠かせない役割を果たしているのが「広報誌」。
広報誌は単なるお知らせの寄せ集めではありません。
地域の人々に情報を伝え、活動を知ってもらい、共感を呼び、参加を促す。
言ってみれば、「地域の心臓」とも言える存在です。
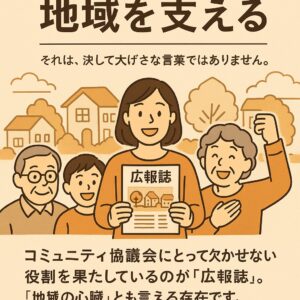
コミュニティ協議会とは?
まず、改めて「コミュニティ協議会」とは何でしょうか?
一言で言えば、**地域住民のために地域住民が主体となって運営する「まちづくり組織」**です。
自治会や町内会、民生委員、子ども会、婦人会、防犯・防災組織、スポーツ団体など、
地域のあらゆる団体や個人が手を取り合い、
「この町をよりよくしたい」という共通の想いで活動を行っています。
具体的には──
-
地域の防災訓練や避難訓練の企画・運営
-
高齢者の見守り活動、福祉事業の推進
-
子どもたちの健全育成事業(スポーツ大会・文化教室など)
-
地域イベント(夏まつり、敬老会、文化祭、マルシェなど)の開催
-
環境美化活動(公園清掃、花壇づくり、ゴミ拾い運動など)
-
地域資源を活かしたまちおこし活動(観光PRや特産品振興)
これらを企画し、実行しているのがコミュニティ協議会です。
なぜ「コミュニティ協議会」が必要なのか?
現代社会は、都市化や人口減少、核家族化の影響で、
地域のつながりが急速に希薄になっています。
かつては当たり前だったご近所づきあい。
困ったときに助け合える関係。
「顔の見える安心感」。
それが、少しずつ失われつつある今、
改めて「地域で支え合う力」が求められています。
災害時の助け合いも、防犯も、高齢者支援も、
行政だけに任せることはできません。
私たち一人ひとりが地域に関心を持ち、
互いに支え合う仕組みが不可欠なのです。
コミュニティ協議会は、まさにそのために存在します。
行政ではカバーしきれない**「地域の細かなニーズ」**に寄り添い、
住民の力で課題を解決していく。
つまり、
地域の自立的な力=コミュニティ協議会の力
と言っても過言ではありません。
広報誌の役割とは?
そんな大切な活動を、地域住民に伝え、
理解と共感を広げるために欠かせないのが、広報誌です。
広報誌には、次のような役割があります。
-
地域活動をわかりやすく伝える
-
活動に対する共感・協力を呼びかける
-
地域への参加意識を育てる
-
住民同士のつながりを深める
-
外部へ地域の魅力を発信する
例えば、春に開催した「花いっぱい運動」。
どれだけの人が参加して、どんな笑顔があふれたのか。
写真と一緒に紹介すれば、
「ああ、こんな素敵な活動があったんだ」と地域の人々が温かい気持ちになります。
また、広報誌に載った活動をきっかけに、
「次は私も参加してみようかな」と思う人が出てくるかもしれません。
広報誌は単なる記録ではありません。
**未来の参加者を育てる「種まき」**なのです。
なぜ今、広報誌がますます重要なのか?
今、広報誌の存在意義はますます高まっています。
理由は大きく3つあります。
(1)地域コミュニティの希薄化への対策
「隣に誰が住んでいるか知らない」
そんな声も聞かれる現代。
広報誌は、地域の情報を通じて、住民同士のつながりを育む大切な手段です。
(2)正確な情報発信手段
ネットやSNSには情報があふれていますが、
地域のことはやっぱり「地域発」の情報が一番安心。
広報誌は、住民にとって信頼できる情報源となります。
(3)リアルな「紙媒体」の力
デジタル時代だからこそ、
紙の持つ信頼感・安心感・あたたかみが見直されています。
特に高齢者世代には、
「家に届く広報誌」を楽しみにしている人が少なくありません。
広報誌づくりは「地域の未来を育てる仕事」
広報誌をつくるということは、
単に「行事の報告」をまとめるだけではありません。
-
地域の今を記録し、
-
未来への思いを伝え、
-
次の世代へバトンをつなぐ
そんな、**「まちの歴史を紡ぐ仕事」**でもあります。
たとえば、
10年後、20年後に、
「この地域にはこんな素敵な活動があったんだね」と
後世の人たちが手に取る資料にもなるかもしれません。
あなたがいま手がけている広報誌は、
間違いなく、地域にとってかけがえのない財産になるのです。
「うまく作れるか不安…」そんなあなたへ
でも、広報誌作りは、簡単な仕事ではありません。
-
何を書けばいいのか
-
誰にお願いすればいいのか
-
レイアウトはどうすればいいのか
-
印刷や配布はどう手配するのか
初めて担当になった方なら、なおさら不安に思うはずです。
大丈夫です。
このブログでは、広報誌作成の基本ステップから、
よくあるお悩みの解決策、
すぐに使える文例テンプレートまで、
まるごとサポートする完全ガイドをお届けします!
あなたの「地域を大切にしたい」という想いに、
私たち新潟フレキソも、全力で寄り添います。
一緒に、
「この町に生まれてよかった」と思える広報誌をつくっていきましょう!
2.広報誌作成の基本ステップ|迷わず進める7つの流れ
広報誌づくり。
「何から手をつけたらいいかわからない!」
そんな声を、私たちは何度も耳にしてきました。
でも安心してください。
広報誌作りには、しっかりとした**「基本の流れ」**があります。
このステップに沿って進めれば、初めてでもスムーズに進めることができます!
ここでは、広報誌作成の王道ステップを7つに分けて、
具体的に、わかりやすくご紹介します。
① まずは「企画」を立てよう!
広報誌づくりは、いきなり原稿を書き始めるわけではありません。
最初にすべきは、**「企画」**です。
-
どんなテーマでまとめるか?
-
どんな内容を載せるか?
-
いつ発行するか?
-
誰に読んでもらいたいか?
これらを整理して、広報誌の設計図を作りましょう。
例えば──
・年4回発行なら、季節の行事に合わせた特集を組む
・年1回なら、地域の1年間の活動を総まとめにする
この**「方向性の設定」**が後々の作業をグッと楽にしてくれます。
企画の具体例
-
春号:花まつりレポート、防災訓練案内
-
夏号:夏祭り特集、子ども会活動紹介
-
秋号:敬老会レポート、秋のスポーツ大会
-
冬号:クリスマスイベント、1年の活動総まとめ
② 原稿集め・取材
企画が決まったら、次は中身作りです。
広報誌は、1人で全部書く必要はありません!
各団体の代表、行事の担当者、参加者の声など、多くの人から情報を集めて紙面を作っていきます。
原稿集めのポイント
-
事前に「○○字以内でお願いします」と伝える
-
締め切りを必ず設定する(できれば早めに)
-
写真も一緒にお願いすると紙面が華やかに!
どうしても原稿が集まらない時は、
「5行だけでもいいのでコメントをください」とお願いするだけでも違います。
また、簡単なインタビュー形式(質問3つくらい)で取材し、
こちらでまとめる方法もおすすめです。
③ レイアウト・デザインを考える
集まった原稿や写真を、どう配置するか?
ここがセンスの見せどころですが、難しく考える必要はありません!
まずは
**「読みやすく、わかりやすく」**を第一に考えましょう。
レイアウトのコツ
-
大きな写真を効果的に使う(1ページ1枚でもOK)
-
見出しをしっかりつける(記事が何の話かわかりやすく)
-
長文になりすぎない(1記事あたり500〜800字目安)
-
できれば「2〜3色」くらいでシンプルにまとめる
パワーポイントやWordでも十分作れますし、
本格的な仕上がりを目指すなら、新潟フレキソにご相談ください!
デザインサポートもバッチリ対応します。
④ 校正・確認は念入りに!
原稿が完成したら、絶対に**「校正」**をしましょう。
校正とは、誤字脱字や間違いをチェックする作業です。
校正のチェックポイント
-
名前の漢字(特に注意!)
-
日付・曜日・時間
-
イベント名・団体名
-
写真キャプション(説明文)
1人でチェックするだけでなく、
複数人で読むことがとても大事です。
できれば、
「文章を読んでいない人」が読むとミスを発見しやすいです!
⑤ 印刷に向けた準備
校正まで終わったら、いよいよ印刷の準備!
印刷会社に出す際は、次のポイントをまとめておくとスムーズです。
印刷会社への指示ポイント
-
サイズ(A4?A3二つ折り?)
-
ページ数(4P?8P?)
-
用紙の種類(光沢紙?マット紙?)
-
部数(何部必要?)
-
納品日・納品先
ここがモタつくと、発行スケジュールが狂うので、
できるだけ早めに相談しておきましょう。
新潟フレキソなら、こうした事前相談からしっかりサポートできます!
⑥ 印刷・製本・納品
印刷工程に入ったら、あとは完成を待つのみ。
でも、細かい部分まで気を配ることで、より良い仕上がりになります。
例えば──
-
中綴じ(ホチキス留め)製本にするか?
-
折り加工だけにするか?
-
配布用にまとめて袋詰めするか?
広報誌の配布方法に応じて、最適な形を選びましょう。
⑦ 配布・活用!
完成した広報誌は、いよいよ配布スタート!
-
全戸配布(自治会回覧板、ポストインなど)
-
地域施設への設置(公民館、学校、病院、スーパーなど)
-
イベント時の配布(お祭り、防災訓練など)
さらに、最近では
「デジタル版(PDF)をホームページにアップする」
なんて活用方法も増えています!
より多くの人に読んでもらえる工夫を、ぜひ取り入れてみましょう。
■ まとめ|段取りを押さえれば広報誌作りは怖くない!
ここまで、広報誌作りの基本ステップを紹介してきました。
一見大変そうに思えるかもしれませんが、
段取りを押さえてひとつずつ進めれば、必ず完成にたどり着けます!
しかも、広報誌は「形に残る地域の宝物」。
作るたびに、地域への誇りと愛着がきっと深まります。
そして、もし「自分たちだけじゃ難しいかも…」と感じたら、
プロに頼るのも大事な選択肢。
新潟フレキソなら、
企画段階から、原稿チェック、デザイン制作、印刷・製本まで、
トータルサポートであなたの広報誌づくりを応援します!
次の章では、さらに実践的な──
「広報誌によくある掲載内容のアイデア集」
を紹介していきます!
楽しみに進んでいきましょう!
3.広報誌によくある「掲載内容」アイデア集|ネタ切れ知らず!
広報誌作りでいちばん悩むのが、「何を載せたらいいか」という問題です。
毎回マンネリになったり、ネタが思い浮かばなかったり……担当者さんなら、一度は経験があるはず。
でも、大丈夫。
地域には、伝えたいこと、知ってほしいことがたくさんあります!
ここでは、実際に多くのコミュニティ協議会で掲載されている、鉄板&オススメのネタリストを大公開します!
① 年間行事・イベントレポート
地域の活動をリアルに伝える絶好のチャンス!
例
-
春の花植え運動
-
夏祭り・盆踊り大会
-
秋のスポーツフェスティバル
-
冬のクリスマスイベント、防災訓練
ポイント
-
写真を多めに載せると◎
-
参加者のコメントを一言入れると、より親近感UP!
② これからのイベント案内・募集
未来に向けた「呼びかけ」は超重要。
次回の参加者を増やすためにも、しっかり情報発信しよう!
例
-
町内清掃ボランティアの募集
-
高齢者向け体操教室のお知らせ
-
地域マルシェ開催予告
-
防災訓練参加者募集
ポイント
-
日時、場所、持ち物などをわかりやすく!
-
難しそうなイベントは「初心者歓迎!」と一言添えると参加率UP!
③ 地域の話題・トピックス紹介
地域で話題になっていること、知ってもらいたいことも広報誌の大事な役割!
例
-
新しくできたお店の紹介
-
地域の名所再発見ツアー
-
伝統行事・文化の紹介
-
地元で活躍する人のインタビュー
ポイント
-
小さな話題もOK!「この町でこんなことがあったよ」という温かい情報が好まれる
④ 住民紹介・人物ピックアップ
地域には素敵な人がたくさん。
「顔の見える地域づくり」には、住民紹介がとても効果的!
例
-
長年活動を続ける自治会長さん
-
スポーツで活躍する小学生
-
手作りマルシェを開いた主婦グループ
-
町の歴史を知るご長寿さん
ポイント
-
写真+簡単なプロフィール(出身、趣味、地域への思い)を載せると読みごたえUP!
⑤ 防災・防犯情報
地域を守るために、防災・防犯意識を高める情報もぜひ載せたいところ。
例
-
災害時の避難場所マップ
-
防犯パトロール隊活動レポート
-
火災予防週間のお知らせ
-
高齢者向け詐欺対策情報
ポイント
-
「いざという時にすぐ役立つ情報」を意識してまとめよう!
⑥ 子ども・高齢者向け情報
誰もが安心して暮らせる地域づくりへ。
特に子ども、高齢者向けの取り組み情報は喜ばれます。
例
-
子ども会活動紹介
-
介護予防体操教室レポート
-
親子ふれあいイベント告知
-
敬老会のお祝いメッセージ特集
ポイント
-
子ども向けはカラフル&元気な紙面に!
-
高齢者向けは文字を少し大きめ&わかりやすく!
⑦ コラム・読み物・ミニ特集
少し余白ができたら、「ちょっと読める楽しいコーナー」を入れよう!
例
-
地域の昔話・伝説紹介
-
四季折々の自然写真ギャラリー
-
まちクイズ(例:「○○公園はいつできたでしょう?」)
-
簡単レシピ紹介(地元野菜を使った料理など)
ポイント
-
あえて「脱・情報」な柔らかいネタも入れると、紙面にリズムが出る!
■ 【まとめ】広報誌に「正解」はない!でも大事なのは「伝えたい想い」
広報誌に載せる内容に、絶対的な正解はありません。
大事なのは、
「この町をもっと好きになってもらいたい」
「こんな素敵な活動があることを知ってほしい」
そんなあなたの想いを込めること。
このアイデア集をヒントに、
世界にひとつだけの、あなたの地域の広報誌を作っていきましょう!
【広報誌の基本構成 一覧表】
| 項目 | 内容説明 | ポイント |
|---|---|---|
| 表紙 | 広報誌の顔。タイトル・号数・発行日・目次などを掲載 | 写真やイラストでパッと目を引くデザインに! |
| 巻頭あいさつ | 会長・代表者などの挨拶メッセージ | 地域への感謝や今後の抱負を、短く温かい言葉でまとめる |
| 年間行事・イベントレポート | 直近の行事やイベントの様子を報告 | 写真たっぷり!参加者の笑顔を伝える |
| これからのイベント案内 | 今後開催予定のイベント・行事情報 | 日時・場所・対象・持ち物など、具体的にわかりやすく |
| 地域トピックス | 新しいお店紹介、話題のニュース、地域の豆知識など | 読者に「へえ!」と思ってもらえる話題を選ぶ |
| 住民紹介・インタビュー | 地域で活躍する人や注目の人物を紹介 | 短いインタビュー形式+写真付きが親しみやすい |
| 防災・防犯情報 | 避難所案内、防犯活動、災害への備えなど | すぐに役立つ実用情報をわかりやすく掲載 |
| 子ども・高齢者向けコーナー | 子ども会活動、敬老会、福祉情報、健康教室の案内など | イベント告知やレポート+やさしい表現でまとめる |
| コラム・読み物 | 地域の歴史、昔話、季節の話題、クイズ、レシピ紹介など | 軽く読める「お楽しみコーナー」で紙面に変化をつける |
| 最後のまとめ・編集後記 | 編集メンバーから一言、次号予告など | 読者への感謝+次回へつながる期待感を込める |
4.広報誌に使える「文例テンプレート」集|そのまま使える!
ここでは、
3章で紹介した掲載アイデアに対応した、
広報誌にすぐ使えるテンプレート文例をドドンと紹介していきます!
書き出しに悩んだとき、
締め方に迷ったとき、
この文例を参考にしてください!
① 【年間行事・イベントレポート】テンプレ
【例:春の花いっぱい運動レポート】
【タイトル】
春の陽気に包まれて──花いっぱい運動を実施しました!
【本文】
4月◯日、地域の皆さまのご協力のもと、恒例の「花いっぱい運動」を実施しました。
当日は朝から暖かな春の日差しに恵まれ、町内各地に笑顔が広がりました。
開始の合図とともに、参加者たちは手にスコップやジョウロを手に取り、
用意された色とりどりの花苗を大切そうに植えていきました。
小さなお子さんたちも、お父さんお母さんと一緒に土を掘り、苗をそっと植える姿が見られ、
そのたびに周囲から「上手だね!」と声がかかるなど、
和やかな雰囲気に包まれました。
作業が一段落すると、皆で一休み。
地域の有志の方が用意してくださった温かいお茶と、手作りのお菓子を囲みながら、
世代を超えた交流のひとときが生まれました。
普段あまり話す機会のない近所の方と顔を合わせ、
「うちの子も◯◯小学校なんですよ」
「今度の防災訓練も一緒に参加しましょう」
といった会話も弾み、地域のつながりがさらに深まった様子でした。
今回植えた花々は、これから季節の移ろいとともに、
町内の道路沿いや公園、公共施設前を華やかに彩ってくれることでしょう。
ぜひ、皆さんもお近くを通りかかった際は、
一輪一輪に込められた「地域を想う気持ち」を感じていただければ嬉しいです。
ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!
これからも、住みよい地域づくりのために、力を合わせていきましょう。
【ポイント】
-
日付・天候・参加者層を必ず入れる
-
写真とセットで載せると最高!
② 【これからのイベント案内】テンプレ
【例:防災訓練のお知らせ】
【タイトル】
もしもの時に備えよう──地域防災訓練のお知らせ
【本文】
「災害は忘れたころにやってくる」と言われるように、
私たちの暮らす地域も、常に自然災害と隣り合わせです。
もしもの時に自分と大切な人の命を守るために──
今年も、地域防災訓練を開催します!
【防災訓練 詳細】
日時:9月◯日(日) 午前9時スタート
場所:◯◯公園 集合
持ち物:動きやすい服装・タオル・飲み物・防災意識!
今回の訓練では、地震を想定した避難訓練を中心に、
初期消火訓練、救急救命体験、非常食の試食体験も行う予定です。
また、地域消防団による「放水訓練デモンストレーション」も予定しており、
小さなお子さんにもわかりやすく、防災の大切さを体感していただけます。
初めての方や、体力に自信のない方も安心してご参加いただけるよう、
スタッフがサポートいたします。
特にご高齢の方、小さなお子さま連れの方も、ぜひご家族一緒にご参加ください。
地域で顔を合わせ、助け合う関係を築くきっかけにもなります。
また、当日は訓練終了後に、防災備品の展示・説明コーナーも設けます。
ご自宅の備えを見直すきっかけにもなりますので、ぜひお立ち寄りください。
万一の備えは、日頃の意識から。
一人ひとりの小さな一歩が、地域全体の大きな力になります。
皆さまのご参加を、心よりお待ちしています!
【ポイント】
-
日時・場所・持ち物は必ず太字or囲みで目立たせる
-
「初心者歓迎!」などハードルを下げる言葉を添える
③ 【地域の話題・トピックス紹介】テンプレ
【例:新しくできたパン屋さん紹介】
【
【タイトル】
地域に新しい風──ベーカリー「こむぎ堂」がオープンしました!
【本文】
このたび、◯丁目の角地に、待望の新しいベーカリー「こむぎ堂」がオープンしました!
オープン初日から、焼きたてパンの香ばしい香りに誘われて、多くの住民の方が訪れ、
お店の前にはにぎやかな行列ができるほどの盛況ぶりでした。
「こむぎ堂」は、地域の食材にこだわったパン作りをモットーにしており、
地元の小麦や旬の野菜をふんだんに使った安心・安全なパンがずらりと並びます。
おすすめは、地元産米粉を使ったもっちり食感の食パンと、
毎朝焼き上げる季節の野菜フォカッチャ。
店内に設けられた小さなイートインコーナーでは、
購入したパンと一緒に、オリジナルブレンドコーヒーを楽しむこともできます。
店主の◯◯さんは、
「地域の皆さんに愛される、第二の台所のようなお店にしたい。
子どもたちからお年寄りまで、毎日気軽に立ち寄ってもらえたらうれしいです」
と笑顔で語ってくれました。
今後は、地域イベントとのコラボ出店や、子ども向けのパン教室開催も計画しているとのこと。
町の新たな憩いの場として、ますます賑わいそうです。
近くを通りかかった際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね!
【ポイント】
-
新しいお店・スポット紹介は短くてもOK
-
「店主の一言コメント」があるとぐっとリアルになる!
④ 【住民紹介・人物ピックアップ】テンプレ
【例:自治会長さんインタビュー】
【タイトル】
「みんなで支え合う町に」──◯◯自治会長にインタビュー!
【本文】
今年度より、◯◯地区自治会の会長に就任された◯◯さんに、
地域活動への思いや、今後の抱負を伺いました。
「私はこの町で生まれ育ち、たくさんの人にお世話になってきました。
だから今度は、少しでも地域に恩返しをしたいという気持ちで、
自治会長を引き受けさせていただきました。」
と語る◯◯さん。
これまでにも、町内清掃活動や防災訓練に積極的に参加されてきた◯◯さんは、
「顔と顔が見える関係づくり」を何よりも大切にしています。
「普段から挨拶を交わすだけでも、防犯や防災の意識は格段に高まります。
何か困ったことがあった時に、”あの人に相談してみよう”と思える地域でありたいですね。」
と、力強く語ってくれました。
また、今後力を入れたい活動について尋ねると、
「子どもたちや若い世代にも、もっと地域に関わってもらえるような工夫をしたいです。
例えば、子ども会と連携してイベントを増やすとか、SNSでの情報発信も検討しています。」
と、未来に向けた意欲的なプランを話してくれました。
最後に地域の皆さんへメッセージをお願いすると、
「自治会は決して堅苦しいものではありません。
みんなで力を合わせて、笑顔あふれる町をつくっていきましょう!」
と、温かいエールを送ってくれました。
これからの自治会活動に、ぜひご期待ください!
【ポイント】
-
短いインタビュー形式が読みやすい
-
最後に「応援しています!」などの温かい締めを!
⑤ 【防災・防犯情報】テンプレ
【例:災害時避難場所のお知らせ】
【タイトル】
もしもの時のために──避難場所を改めて確認しましょう!
【本文】
自然災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。
いざという時に自分自身と大切な人の命を守るために、
改めて地域の避難場所を確認しておきましょう!
【避難場所一覧】
-
◯丁目地区:◯◯小学校 体育館
-
△丁目地区:△△公園 管理棟
-
□丁目地区:□□区民センター 2階ホール
避難する際は、家族全員がこの情報を把握していることが大切です。
特に高齢のご家族や小さなお子さんがいる場合は、
いざというときにすぐに移動できるよう、事前にルートを一緒に歩いておきましょう。
また、非常時には、電気や水道などのインフラが止まる可能性もあります。
避難所では最低限の生活物資が配られる場合もありますが、
できるだけ各自で非常持ち出し袋(飲料水・非常食・懐中電灯・充電器など)を備えておくことをおすすめします。
地域の防災訓練にも積極的に参加し、
顔の見える関係を築いておくことで、いざという時に助け合う力がぐっと高まります。
「備えあれば憂いなし」。
今一度、家族で防災について話し合うきっかけにしてみてください!
【ポイント】
-
具体的な施設名を明記する
-
「事前準備の大切さ」を一言添えると◎
⑥ 【子ども・高齢者向け情報】テンプレ
【例:親子ふれあいイベント案内】
【タイトル】
親子で楽しもう!──ふれあいスポーツデー開催のお知らせ
【本文】
「親子で一緒に体を動かして、楽しい思い出を作りませんか?」
そんな思いを込めて、今年も「ふれあいスポーツデー」を開催します!
運動が苦手な方でも楽しめる、簡単で誰でも参加できる種目をご用意しました。
【イベント詳細】
日時:5月◯日(土) 午前10時〜正午
場所:◯◯運動公園 多目的広場
持ち物:動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物
【プログラム内容】
-
親子玉入れ競争
-
みんなでジャンボリレー
-
大縄跳びチャレンジ
-
レクリエーションゲーム(景品あり!)
当日は、子どもたちには参加賞としてかわいい記念品もご用意しています。
また、保護者向けにも、日頃の運動不足解消に役立つストレッチ体験コーナーを設けます!
普段は忙しくてなかなか一緒に遊べない親子の皆さんも、
この機会にたっぷりふれあいながら、楽しい汗を流してみませんか?
小さなお子さまから小学生、高齢の方まで、
「できる範囲で、無理せず楽しく!」をモットーにしていますので、
ぜひご家族揃ってご参加ください!
たくさんの笑顔と元気な声に包まれる一日になりますように──
皆さまのお越しを心よりお待ちしています!
【ポイント】
-
「親子で楽しむ」「笑顔」のキーワードを入れると親しみやすい
⑦ 【コラム・読み物・ミニ特集】テンプレ
【例:ミニコラム「この町の小さな歴史」】
【タイトル】
知っていますか?──「◯◯公園」の名前に込められた歴史
【本文】
皆さんおなじみの「◯◯公園」。
家族で散歩をしたり、子どもたちが元気に遊んだりと、地域の憩いの場となっていますが、
その名前に込められた由来を知っている方は、意外と少ないかもしれません。
実は「◯◯公園」という名前は、
今からおよそ150年前、この地に祀られていた「◯◯大明神」という神社にちなんだものです。
当時は、地域の守り神として親しまれ、季節ごとの祭礼では、
近隣の村々からも多くの人が集まり、大いに賑わったと記録されています。
戦後、宅地化の波の中で神社はやむなく移転となりましたが、
「この地の歴史を忘れないように」との想いから、
新たに整備された公園に、かつての神社の名前が冠されたのだそうです。
今も、◯◯公園の片隅には、ひっそりと残る小さな石碑が、
かつてここにあった神社と、先人たちの祈りの心を伝えています。
何気なく通り過ぎる場所にも、
長い時間をかけて育まれてきた地域の物語が刻まれています。
これからも、身近な町の歴史に目を向け、大切にしていきたいですね。
【ポイント】
-
軽く読める分量で「へえ!」と思える内容を意識
■ 【まとめ】テンプレを活かして、あなたの「広報誌らしさ」を!
これらのテンプレは、あくまで「たたき台」です。
少しアレンジしたり、地域らしい言葉を入れたりして、
あなたの地域にぴったり合った広報誌をつくっていきましょう!
読んだ人の心に、
「あったかいな」「うちの町、いいな」
そんな想いが広がるように。
次の章では、広報誌をさらにレベルアップさせる
「魅力的にするためのコツ」
を紹介していきます!
5.広報誌を魅力的にするコツ|読まれる!伝わる!愛される!
せっかく作った広報誌、
どうせなら「手に取ってもらいたい」「読んでもらいたい」「地域をもっと好きになってほしい」と思いますよね。
そのためには、ちょっとした工夫がとても大切です!
ここでは、
ただ情報を並べるだけではない、
「伝わる広報誌」にするための具体的なコツを、
実例・アクション付きでご紹介します!
① 写真を「主役」にしよう
広報誌の第一印象を決めるのは、文章よりも写真です。
写真には、
・地域の活気
・行事の楽しさ
・人と人とのつながり
そんな”空気感”を一瞬で伝える力があります。
実践アクション
-
イベントでは「人の表情」がわかる写真を意識して撮る
-
笑顔・作業中・みんなで並んでいる場面は鉄板
-
1イベントあたり最低3~5枚は押さえる
-
引きの写真+寄りの写真をバランスよく使う
【ポイント】
人のいない写真ばかりだと「寂しい」印象になるので注意!
多少ピントが甘くても、表情が生きている写真を優先しよう!
② 見出し・タイトルで「心をつかむ」
たとえば、
「第3回避難訓練レポート」
よりも、
→「地域の絆を再確認!──第3回避難訓練レポート」
の方が、読んでみたくなりませんか?
タイトル・見出しは、
一瞬で内容と魅力が伝わる工夫をしましょう!
実践アクション
-
「感情」を込める(わくわく、ホッとする、誇りに思う、など)
-
「!」や「──」を使ってリズムを出す
-
報告だけじゃなく、「呼びかけ型」「問いかけ型」のタイトルも試す
【ポイント】
特にトップ記事や表紙は、タイトルだけでワクワクさせよう!
③ 文章は「短く、やさしく、あたたかく」
広報誌の読者は老若男女、様々な世代。
だからこそ、誰が読んでもわかる言葉選びが大切です。
専門用語や長い言い回しは避けて、
できるだけ短く、簡潔に、やさしい言葉でまとめましょう。
実践アクション
-
1文は50文字以内を目安に
-
「です・ます」調で統一(読みやすさ重視)
-
難しい言葉は使わず、かみ砕く(例:「防災訓練=もしもの備えの練習」)
【ポイント】
文章にちょっと「笑顔を込める」イメージで書くと、
読む人にやさしさが伝わる!
④ デザインは「シンプル&わかりやすく」
デザインに凝りすぎると、かえって読みにくくなってしまいます。
大切なのは、情報をきちんと伝えること。
紙面に「空白」をうまく使い、
読みやすいレイアウトを心がけましょう。
実践アクション
-
1ページにテーマは1つ(ごちゃごちゃさせない)
-
文字の大きさは見出し>本文でメリハリを
-
色は2~3色以内にまとめる(カラフルすぎ注意)
【ポイント】
読んだ時に「疲れない」レイアウトを目指そう!
⑤ 「読者の目線」で作る
「作り手の自己満足」になってしまうと、読まれません。
常に、読む人の目線に立つことが大事です。
実践アクション
-
紙面を作ったら「自分が住民のつもり」で一度全部読む
-
「これ、誰が興味を持つ?」「何が伝わる?」と自問する
-
お年寄りや子どもにも届く内容か意識する
【ポイント】
読者にとって「うれしい・ためになる・誇れる」広報誌を目指そう!
⑥ 「顔出しOK」の人物写真を多めに使う
広報誌の紙面に、地域の人の顔がたくさん載っていると、
それだけで親近感が湧きます。
「私の知り合いが載ってる!」
「うちの孫が写ってる!」
それだけで、ページをめくる手が止まらなくなるんです。
実践アクション
-
イベント参加者には「顔出しOKですか?」と確認をとる
-
グループ写真だけでなく、個人のアップも数枚使う
-
写真の下に名前やひとことコメントを添えるとさらに◎
【ポイント】
地域の「人」が主役の紙面を作ろう!
■ 【まとめ】広報誌づくりは「愛情」がすべて!
広報誌を魅力的にするために、
小手先のテクニックはいくらでもあります。
でも、何よりも大切なのは、
**「この町が好き」「もっと良くしたい」**という気持ち。
その愛情が、文章や写真、デザインの隅々に自然とにじみ出て、
読む人に届くのです。
だから、うまく作ろうと気負いすぎなくても大丈夫。
あなたの想いを込めて、一生懸命作れば、
それは必ず伝わります!
このあとの章では、
**広報誌担当者さんからよく寄せられる「お悩みQ&A」**を紹介していきます!
「こんなときどうすれば?」を一緒に解決していきましょう!
6.【必見】広報誌担当者さんのための「よくあるお悩みQ&A」
広報誌作りは、やってみるとわかる通り、
想像以上にいろんな壁にぶつかります。
-
原稿が集まらない
-
デザインが難しい
-
納期に間に合うか不安
-
そもそも何から始めたらいいかわからない…
そんな悩みに応えるべく、
ここでは広報誌担当者さんからよく寄せられる「お悩み」をピックアップ!
具体的な解決策とともに、一問一答形式でまとめました!
Q1:原稿がなかなか集まりません。どうしたらいいですか?
A:集まる仕組みを作りましょう!
「〇〇字以内でお願いします」「〇月〇日締め切りです」
とだけ伝えても、なかなか集まりません。
解決アクション
-
最初から「テンプレート」を渡す
(例:「行事名」「一言コメント」「写真1枚」を提出) -
締め切りを「余裕を持って」設定する(最低2週間前!)
-
個別に声をかける(LINEや電話で「お願い」すると効果大)
-
「5行だけでもいいので!」とハードルを下げる
【ポイント】
「全部ちゃんと書かないといけない」と思わせない。
“少しでもOK”の姿勢が大事!
Q2:デザインなんてできません!どうすればいいですか?
A:シンプル is BEST!プロに相談もアリです!
デザインにこだわるあまり、広報誌作りが止まってしまうのはもったいない!
まずは「読みやすさ」「わかりやすさ」だけ意識すれば十分です。
デザインソフトが使えなくても、Wordやパワポで作成可能です!
解決アクション
-
A4用紙に「見出し・本文・写真」を手書き配置してイメージを作る
-
フォントサイズと色を統一(見出し大、本文中)
-
欲しい雰囲気を印刷会社に相談する(「明るく!」「元気な感じで!」とか)
【ポイント】
プロ(新潟フレキソ)に「デザインサポート」を頼めば、さらに安心!
Q3:何を書いたらいいかわかりません…
A:広報誌の「型」を作ろう!
記事の型が決まっていれば、
あとは中身を当てはめていくだけ!
解決アクション
-
毎回「イベントレポート」「お知らせ」「人物紹介」など項目を固定する
-
行事ごとに「誰が何をした?どう思った?」の流れで書く
-
写真+コメントだけでも1ページ埋まる!
【ポイント】
「パターン化」すれば、担当が変わってもスムーズに続けられる!
Q4:配布部数が少ないけど、印刷頼めますか?
A:もちろん大丈夫です!
「広報誌なんて数百部しかないから…」とためらう必要はありません!
新潟フレキソでは、小ロット印刷もバッチリ対応しています!
解決アクション
-
最低ロットを事前に相談(100部からでもOK!)
-
ついでにデータ保存をお願いしておくと、次号が楽!
【ポイント】
「部数が少ないから割高になりそう」と心配する前に、まずは相談を!
Q5:スケジュール管理が不安です。間に合うか心配…
A:逆算スケジュールを組みましょう!
広報誌づくりは、”何となく進める”と必ずバタバタします。
最初に「納品日から逆算」でスケジュールを作りましょう!
解決アクション
-
納品希望日をまず決める(例:7月1日配布なら6月20日納品)
-
印刷にかかる日数を確認(通常7~10日見ておく)
-
校正・修正にかかる時間も確保(最低1週間)
-
原稿締め切りはさらに前倒し!(最低2~3週間前)
【ポイント】
スケジュール表を印刷してチーム共有すると、抜け漏れ防止になる!
Q6:写真撮影が苦手です。どうしたらいいですか?
A:スマホでも十分!コツは「枚数」と「タイミング」!
プロ並みのカメラがなくても大丈夫。
スマホでも、ポイントを押さえれば十分きれいな写真が撮れます!
解決アクション
-
「人物が中心」の写真を多めに撮る
-
イベント最初、中盤、終盤でそれぞれ撮影
-
なるべく自然な表情を狙う(ポーズより自然体!)
【ポイント】
「撮れたらラッキー」じゃなく、
「何枚も撮って、その中からベストショットを選ぶ」が基本!
■ 【まとめ】不安は”行動”で解消できる!
広報誌作りには、悩みや不安がつきものです。
でも、ひとつひとつ小さなアクションを積み重ねていけば、
必ず乗り越えられます!
そして、困ったときは、
プロに頼るのもひとつの賢い選択。
新潟フレキソでは、
-
スケジュール相談
-
デザインサポート
-
小ロット印刷
-
データ保存サービス
など、
広報誌づくりをトータルでサポートしています!
次の章では、そんな印刷をプロに頼むメリットについて、
もっと詳しくご紹介していきます!
一緒に、最高の広報誌をつくっていきましょう!
7.印刷をプロに頼むとここが違う!|安心・キレイ・効率的
広報誌作り。
自分たちだけでがんばるのも素晴らしいけれど、
**「プロに頼む」**という選択肢を持っておくと、
広報誌のクオリティも、作る人の心の余裕も、ぐっと変わります。
ここでは、
印刷のプロに頼むと何が違うのか?
どんなメリットがあるのか?
を超リアルに紹介していきます!
① データの不備をプロがチェックしてくれる
広報誌のデータ作成でよくあるのが、
「気づかないうちに起きるミス」。
-
写真が低解像度でぼやける
-
文字が端っこで切れる
-
色味がパソコン画面と違う
-
サイズが微妙にずれている
こうした小さなトラブルが、
素人作成では本当に多いです!
プロに頼めば、
-
サイズ・トンボ・解像度チェック
-
色校正(色味確認)
-
最終データチェック
を丁寧にしてもらえるので、
「あれ?なんか仕上がりがイメージと違う…」
みたいな悲劇を防げます!
【ポイント】
ミスが出る前に止める。これがプロの技!
② 小ロットでもコストを抑えられる!
「部数少ないと、ものすごく高くなるんじゃ…」
そんな心配、ありますよね?
でも安心してください。
最近は、小ロット対応が当たり前!
新潟フレキソでは100部からでも大丈夫です!
さらに、部数が少ない分、
-
紙の種類を選んでコスト調整
-
サイズや折り加工を工夫して割安に
なんて提案もできるので、
予算内でベストな広報誌づくりができます!
【ポイント】
「無理にたくさん刷らない」柔軟対応がプロの強み!
③ スピード対応&納期が読める!
プロに頼むと、
**「納期が確実」**という安心感が手に入ります。
自分たちだけだと、
-
校正が遅れた…
-
印刷機が壊れた…
-
用紙が足りない…
といったイレギュラーに対応できないこともありますが、
印刷会社なら、
-
予備日を確保している
-
代替機で対応できる
-
紙の在庫管理も完璧
なので、
**「いつまでに仕上がるか」**が明確です!
【ポイント】
納期遅れの心配ゼロ。イベントに間に合う!
④ 「ちょっとだけ頼みたい」にも対応できる
たとえば──
-
「広報誌のレイアウトだけお願いしたい」
-
「表紙デザインだけプロにお願いして、中身は自分たちで」
-
「印刷だけお願いして、配布は自分たちで」
こんな部分的なサポートも可能です!
全部丸投げじゃなく、
「できるところは自分たちで、難しいところだけプロに」
という柔軟な組み合わせができるのも、
地域密着型の印刷会社ならでは。
新潟フレキソでは、
「ちょっとだけ頼みたい」にも、
すごくフレンドリーに対応してます!
【ポイント】
“お手伝い感覚”で使えるから、初めてでも安心!
⑤ デザイン性・仕上がりがワンランク上がる!
正直に言います。
プロに頼むと、見た目が全然違う。
-
色がきれい
-
写真がシャープ
-
レイアウトが美しい
-
文字組みが読みやすい
広報誌を手に取った瞬間、
「あっ、なんかいいな」
と感じる”質感”が、まったく違うんです。
これ、読み手にもちゃんと伝わります。
そして「いい広報誌作ってる地域だな」と、
地域のイメージアップにもつながる!
【ポイント】
「愛される広報誌」は、仕上がりの美しさから!
⑥ 長期保存・次号制作がぐっと楽になる!
プロに頼めば、
-
データを適切に保存して管理
-
印刷用データ形式でバックアップ
してもらえるので、
次号の制作がめちゃくちゃ楽になります!
「去年の広報誌、データどこいった?!」
なんて大慌てする必要もなし。
さらに、バックナンバーをまとめた「記念冊子化」も簡単にできる!
【ポイント】
1回頼めば、次から加速的にラクになる!
■ 【まとめ】プロに頼むのは「ズル」じゃない!賢い選択!
地域のために、みんなでがんばって作る広報誌。
だからこそ、
-
ミスを減らし
-
ストレスを減らし
-
仕上がりを良くし
-
スムーズに完成させる
そのためにプロに頼るのは、
何も悪いことじゃありません。
むしろ、広報誌担当者さんの大事な選択肢です!
新潟フレキソでは、
-
原稿相談
-
デザインサポート
-
小ロット印刷
-
短納期対応
など、地域のコミュニティ協議会さんを全力でサポート中!
「初めての広報誌で不安…」
「忙しくて時間がない!」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください!
一緒に、
世界に一つだけの、あなたの地域の広報誌をつくりましょう!
8.新潟フレキソが選ばれる理由|地域に寄り添う広報誌づくり
広報誌作り。
それは単なる印刷物の制作ではありません。
-
地域をもっと良くしたい
-
住民同士をつなげたい
-
未来へ思いを伝えたい
そんな大切な想いをカタチにする仕事です。
だからこそ、
私たち新潟フレキソは、
単なる印刷屋ではなく、
**「地域の広報パートナー」**でありたいと考えています。
ここでは、
なぜ新潟フレキソが多くのコミュニティ協議会様に選ばれているのか、
その理由をじっくりご紹介します!
① 地元密着型だから「顔が見える安心感」
新潟フレキソは、
新潟に根を張る印刷会社です。
-
地域の行事
-
地域の文化
-
地域ならではの想い
そうした新潟の空気感を知り尽くしているからこそ、
「地域ならではの伝え方」ができるんです。
全国チェーンの印刷サービスにはない、
**「顔の見える付き合い」**を大切にしています。
打ち合わせも、納品も、サポートも。
すぐそこにいるスタッフが、あなたと一緒に走ります!
【ポイント】
急な変更、細かい相談にも、すぐ対応できるフットワークの軽さ!
② 原稿相談・構成サポートまでできる!
「広報誌を作りたいけど、何を書けばいいかわからない…」
そんなご相談、大歓迎です!
新潟フレキソでは、
単に「データをもらって印刷する」だけじゃありません。
-
記事の構成相談
-
見出し案のアドバイス
-
写真の配置提案
など、
広報誌の設計段階からサポートします!
ちょっとした相談から、
「一緒に考えましょう!」と寄り添うスタイル。
【ポイント】
一人じゃない安心感。
あなたの「伝えたい想い」を一緒にカタチにします!
③ 小ロット・短納期も柔軟対応!
コミュニティ協議会の広報誌は、
-
配布部数が少なかったり
-
イベント直前に必要になったり
-
スケジュールがタイトだったり
「ちょっと特殊」な条件がつきもの。
そんなときこそ、新潟フレキソの出番!
-
100部~OK!
-
短納期対応OK!
-
追加印刷・増刷もスムーズ!
「今からでも間に合いますか?」というご相談も、まずは一度お声がけください!
【ポイント】
「できません」より「どうやったらできるか」を考える会社!
④ 印刷だけじゃない!加工・発送までワンストップ
広報誌制作には、印刷だけでなく
-
折り加工(二つ折り、三つ折り)
-
中綴じ製本(冊子仕上げ)
-
配布先への梱包・発送代行
など、
細かい工程がたくさんあります。
新潟フレキソなら、
すべて一括対応!
担当者さんが、いちいち別業者に依頼したり、取りまとめたりする必要がありません。
【ポイント】
丸投げOK!
あなたは「完成を待つだけ」で広報誌ができあがります!
■ 【まとめ】広報誌作り、一緒に楽しみませんか?
広報誌を作るって、
大変なこともあるけど、
本当は、
めちゃくちゃ楽しいことなんです。
-
地域をもっと好きになる
-
新しい人との出会いがある
-
未来に向けた小さな種をまける
そんな素敵な広報誌づくりを、
あなたと一緒に楽しみたい!
新潟フレキソは、いつでもその準備ができています。
ぜひ、あなたの町の物語を、
一緒にカタチにしていきましょう!
まずは、お気軽にご相談ください!
9.まとめ|あなたの地域の「未来」を、一緒につくりましょう
ここまで、
広報誌作りのステップ、
掲載アイデア、
文例テンプレート、
魅力的にするコツ、
よくあるお悩みとその解決法、
そしてプロに頼むメリットまで──
たっぷりとご紹介してきました。
広報誌作りは、決して簡単な道のりではありません。
企画、取材、編集、校正、印刷……
一つひとつの作業に、地道な努力と工夫が必要です。
でもその先には、
-
地域の人が笑顔で手に取ってくれる姿
-
子どもたちが自分たちの写真を見て喜ぶ瞬間
-
「こんな町に住んで良かった」と感じる温かい時間
そんな、かけがえのない光景が待っています。
■ 広報誌作りは「地域の未来への贈り物」
今日の一冊が、
-
来年の活動への励みになり
-
10年後に地域の歴史を刻み
-
50年後に誇りとなって残るかもしれません。
あなたが作る広報誌は、
単なる印刷物ではありません。
地域の未来への贈り物です。
そんな大切な広報誌作りを、
私たち新潟フレキソは、
全力でサポートさせていただきます。
■ まずはお気軽にご相談ください!
-
何から始めたらいいかわからない
-
デザインやレイアウトに自信がない
-
小ロットだけど頼んで大丈夫?
-
なるべく予算を抑えたい
-
とにかく急ぎで間に合わせたい!
そんなお悩み、すべてOKです。
新潟フレキソなら、
-
企画から相談OK
-
データ作成サポートOK
-
小ロットOK
-
短納期相談OK
-
お見積もり無料・スピード対応OK
地域密着の強みを活かして、
あなたの「こうしたい!」に全力で応えます。
■ お問い合わせはこちらから!
株式会社新潟フレキソは新潟市の印刷会社です。
お気軽にお問い合わせください。
▶ 会社概要はこちら
■ 最後に
このブログをここまで読んでくださったあなたは、
きっと地域のことを、心から大切に想っている方だと思います。
そんなあなたの想いを、
広報誌というカタチにして、
地域に届けていくお手伝いができたら──
これ以上嬉しいことはありません。
一緒に、
世界にひとつだけの、あなたの町の広報誌を作っていきましょう!
▼関連記事はこちらから
